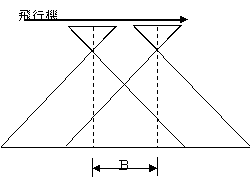| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<H18-5-A�F���>
���ʋ���15cm�A��ʂ̑傫��23cm�~23cm�̍q��J������p���āA�I�[�o�[���b�v60���ŕ�����ȓy�n�̉����ʐ^�̎B�e���s�������B���S�����肵�Ĕ�s�ł���Œx�̑Βn���x������207km�̔�s�@�ŎB�e���邱�ƂƂ��A�V���b�^�[�Ԋu���ŏ��łS�b�Ƃ���ƁA�B�e�\�ȍő�̏k�ڂɍł��߂����̂͂ǂꂩ�B���̒�����I�ׁB
�P�D1/2,500 �Q�D1/3,000 �R�D1/3,500 �S�D1/4,000 �T�D1/4,500 |
|
<H18-5-A�F��>
�B�e���������ʐ^�k�ڂ����߂���ł���B
1.��s���x�ƃV���b�^�[�Ԋu����A�B�e����������߂�B
2.�B�e���������ʐ^�k�ڂ����߂�B
�@�P |
|
<H18-5-B�F���>
��ʋ���15cm�A��ʂ̑傫��23cm�~23cm�̍q��J������p���āA�C�ʂ���̍��x1,600m����W��100m�̕�����ȓy�n���B�e���������ʐ^�ɁA����������2�̍����`�A�a���ʂ��Ă���B�k��1/25,000�n�`�}��ō����`�A�a�Ԃ̋�����29mm�A�ʐ^��ō����`�A�a�̐�[�Ԃ̋�����75mm�Ƃ���ƁA���̍����̍����͂����炩�B�ł��߂����̂����̒�����I�ׁB
�P�D40 m �Q�D45 m �R�D50 m �S�D55 m �T�D60 m |
|
<H18-5-B�F��>
�ʐ^�̎B�e���x�Ək�ڂ̌v�Z�Ɋւ�����ł���B
1.�n�}�̊Ԋu����A���ۂ̍����`�E�a�̊Ԋu�����߂�B 2.�ʐ^��̋����𗘗p���āA������[����̎B�e���x�����߂�B 3.�����̍����i���j�����߂�B ����āA�����̍�����50m�ƂȂ�B
�@�R |
|
<H18-5-C�F���>
���̕��́A�ʏ�̒n�`�}�쐬�̂��߂Ɏg�p�����ʐ^�ɂ��ďq�ׂ����̂ł���B���炩�ɊԈ���Ă�����̂͂ǂꂩ�B���̒�����I�ׁB
�P�D�ʐ^�̎�_�́A�ʐ^�̎l�����͎l�ӂ̊e�����̑�����w�W������_�Ƃ��ċ��߂邱�Ƃ��ł���B �Q�D�ʐ^�̉����_�́A�ʐ^��̍��w�����⍂���̑����狁�߂邱�Ƃ��ł���B �R�D������ȓy�n���B�e�����ʐ^�������ʐ^�łȂ��ꍇ�A��_�A���p�_�A�����_�̏��Ԃł��̒n�_�̑��̏k�ڂ��傫���B �S�D�ʐ^�Ɏʂ��Ă���v�킩��A�J�����̌X���̕����Ƒ傫���̊T����m�邱�Ƃ��ł���B �T�D�N���̂���y�n���B�e�����ʐ^���A���˕ϊ�����ƁA�k�ڂ͎ʐ^�S�̂ň��ɂȂ�B
|
|
<H18-5-C�F��>
�ʐ^�̓����Ɋւ�����ł���B���e���ɂ��čl����ƁA���̂悤�ɂȂ�B
1.�������B 2.�������B 3.�ԈႢ�B 4.�������B 5.�������B
���I���\�t�H�g�Ƃ́A�摜�̂Ђ��݂��Ǖ����Ƃɐ��˓��e�̈ʒu�ɏC�����A���k�ڂɕϊ��������́B
�@�R |
|
<H18-5-D�F���>
���̕��́A�ċG�ɎB�e�����k��1/30,000�̃p���N���}�e�B�b�N�ʐ^�̔��ǂ̌��ʂɂ��ďq�ׂ����̂ł���B���炩�ɊԈ���Ă�����̂͂ǂꂩ�B���̒�����I�ׁB
�P�D���c�n�тɓK�x�̊Ԋu�������č�����������ɕ���ł����̂ŁA���d���Ɣ��ǂ����B �Q�D�J�ɂ���A�K�����Â��A�����Ǝv���镔�����Ƃ����Č������̂ŁA�L�t���Ɣ��ǂ����B �R�D�k�n�̒��ɋK���������i�q��̔z������������炵�����̂��݂�ꂽ�̂ŁA�ʎ����Ɣ��ǂ����B �S�D���H�Ɣ�ׂĊK�����Â��A�������͂�邢�J�[�u��`���Ă����̂ŁA�S���Ɣ��ǂ����B �T�D�R�̉F�^�̑傫�Ȍ����Ɖ^�����v�[���Ȃǂ̎{�݂������~�n���ɂ��邱�Ƃ���A�w�Z�Ɣ��ǂ����B |
|
<H18-5-D�F���>
�ʐ^�̔��ǂɊւ�����ł���B���e���ɂ��čl����ƁA���̂悤�ɂȂ�B
1.�������B 2.�ԈႢ�B 3.�������B 4.�������B 5.�������B
���p���N���}�e�B�b�N�ʐ^�Ƃ͓���Ɠ����x�̊��x�ŎB�e���������̂��Ƃł���B�ߔN�ł́A�ʐ^�����q���摜�ł̎g�p�p�x�������Ȃ��Ă����B
�@�Q |