| 方向観測法による水平角の観測作業 |
| 「方向観測法による水平角の観測作業」は、士補試験に出題される問題の中でも、理解し難い問題の一つと言われています。ここでは、模擬的な方向観測作業と野帳の書き方を見ることにより、少しでも理解しでもらう事を目的としています。 |

|
| ◆ 望遠鏡で"目標1"を視準し、角度を0°0′0″にセットします。 |
 |
 |
トランシットの望遠鏡を目標1に向けます。
望遠鏡固定つまみが接眼レンズ側に来るのが正(r)です。 |
望遠鏡を見るとこのように見えます。 |
 |
ここまでの野帳(データシート)は、
次のように書きます。 |
水平角を0°に合わせます。
Vは鉛直角を表しています。 |
|
| ◆ 望遠鏡で"目標2"を視準し、正(r)の観測を行い、角度を読みます。 |
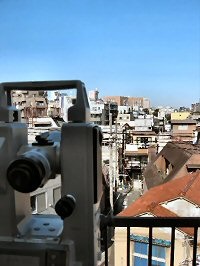 |
 |
| トランシットの望遠鏡を目標2に向けます。 |
望遠鏡を見るとこのように見えます。 |
 |
ここまでの野帳(データシート)は、
次のように書きます。 |
| 水平角を読取ります。 |
|
| ◆ 望遠鏡で"目標3"を視準し、正(r)の観測を行い、角度を読みます。 |
 |
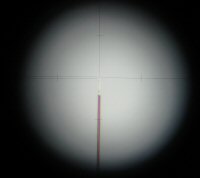 |
| トランシットの望遠鏡を目標3に向けます。 |
望遠鏡を見るとこのように見えます。 |
 |
ここまでの野帳(データシート)は、
次のように書きます。 |
| 水平角を読取ります。 |
|
| ◆ 望遠鏡を 正(r )から 反(l) にします |
 |
 |
 |
"目標3"を視準した後、望遠鏡を回転させます。
今まで、接眼レンズが手前だったのが、対物レンズが手前に来たのがわかります。 |
 |
 |
| 望遠鏡の回転は固定ネジを用います。 |
この時、水平角(H) は変わりません。 |
|
| ◆ 望遠鏡を反(r) にした状態で、目標3を視準します。 |
 |
 |
トランシットを水平方向に回転させ、
望遠鏡で目標3を視準します。
望遠鏡固定ネジは反対側となり見えません。 |
水平方向への回転は、
水平固定ネジみを用います。 |
 |
ここまでの野帳(データシート)は、
次のように書きます。 |
この時の水平角(H) の値は、
126°41′50″に 180°を加えた値となります。
(5″のズレがあります) |
|
| ◆ 望遠鏡を反にした状態で、目標2を視準します。 |
 |
 |
ここまでの野帳(データシート)は、次のように書きます。 |
| 目標2を視準します。 |
この時の水平角(H) の値は、
306°41′55″から減って行きます。
(角度を左回りに測るため) |
|
| ◆ 望遠鏡を反にした状態で、目標1を視準します。 |
 |
 |
ここまでの野帳(データシート)は、次のように書きます。 |
| 目標1を視準します。 |
この時の水平角(H) の値は、
180°00′00″に近くなります。
(写真は丁度になりました) |
|
| ◆ 完成した野帳 |
| 目盛 |
望遠鏡 |
番号 |
視準点 |
観測角 |
計算 |
結果 |
| 0° |
正(r) |
1 |
目標1 |
0°00′00″ |
|
0°00′00″ |
| |
|
2 |
目標2 |
97°52′45″ |
97°52′45"−
0°00′00" |
97°52′45″ |
| |
|
3 |
目標3 |
126°41′50″ |
126°41′50" −
0°00′00″ |
126°41′50″ |
| |
反(l) |
3 |
目標3 |
306°41′55″ |
306°41′55″−
180°00′00″ |
126°41′55″ |
| |
|
2 |
目標2 |
277°52′45″ |
277°52′45″−
180°00′00″ |
97°52′45″ |
| |
|
1 |
目標1 |
180°00′00″ |
180°00′00″−
180°00′00″ |
0°00′00″ |
完成した野帳は、上の通りとなります。ここまでの観測作業は、望遠鏡 正と反 を1回ずつ行っているため、「正反1対回」と言います。
士補試験では、この後、倍角や較差を求めさせることが多く、さらには倍角差や観測差を求め、定められた許容範囲と比較させることもあります。
角度の値は、正と反の値を平均することによって求めることができます。 |
|