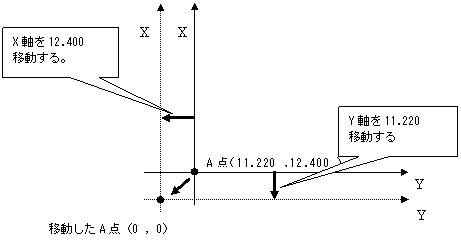| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<H20-7-A:解答>
解答:2 |
|
<H20-7-B:解答>
 求めるべき土地A,F,G,Eは、問題文より長方形であるため、その面積は、35.000 m × x となる。 土地の面積を変えないため、2.で求めた面積を用いて、次の式を組み立てる。 1575.000 ㎡ = 35.000 m × x よって、x = 45.000 m 45.000 + 11.220 = 56.200 よって、点GのX座標は、56.200 mとなる。
解答:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<H20-7-C:解答> No6(応用測量:その他):H19-C・H20-C(出題回数 2/15)
解答:4
|
| <H20-7-D:解答> ● 関連問題(河川の標高計算等) No6(応用測量:河川測量):H10-C・H16-D・H20-D(出題回数 3/15) 法尻や法肩、河床の意味などを理解し、河川の断面図を描ければ比較的簡単に解く事ができる。
上図を参考に次の手順で解けばよい。
1.問題文より、各測点間の勾配が一定であるため、河床部の面積を求める。 A(三角形) = ((3.0×(6.2-4.2))/2 = 3.0 ㎡ B(台 形) = (((6.2-4.2)+(6.7-4.2))×3.0)/2 = 6.75 ㎡ C(台 形) = (((6.2-4.2)+(6.7-4.2))×1.0)/2 = 2.25 ㎡ D(三角形) = ((3.0×(6.2-4.2))/2 = 3.0 ㎡ よって、河床部の面積は、3.0+6.75+2.25+3.0 = 15.0 ㎡
2.河床部の平均標高を求める。 河床部の平均高は、次のように求められる。15.0 ㎡ / (3.0+3.0+1.0+3.0) = 1.5m よって、河床部の平均標高は、次のようになる。 13.2m-(4.2m+1.5m)= 7.5m
解答:3 |