| H17年度 測量士補試験 No6 地図編集 |
|
|
<H17-6-A:問題>
次の文は、地図の投影について述べたものである。 ア ~ オ に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
地図の投影とは、地球上の地物の位置や形をできるだけ正しく ア に描くために考えられたものである。地球の表面は イ であるが、ごく狭い範囲を描く場合を除いて、 イ
上の図形を完全に ア に描くことは ウ であり、必ず エ を生じる。
そのため、地図の投影でば図形の エ を、長さ、角度、 オ の要素について、できるだけ小さくするようにしている。
|
|
ア
|
イ
|
ウ
|
工
|
オ
|
|
1.
|
地 上
|
円 盤
|
可 能
|
転 位
|
面 積
|
|
2.
|
平 面
|
曲 面
|
可 能
|
ひずみ
|
面 積
|
|
3.
|
平 面
|
曲 面
|
可 能
|
ひずみ
|
方 位
|
|
4.
|
地 上
|
円 盤
|
不可能
|
転 位
|
方 位
|
|
5.
|
平 面
|
曲 面
|
不可能
|
ひずみ
|
面 積
|
|
|
|
<H17-6-A:解答>
地図の投影に関する文章である。問題文のア~オについて考えると次のようになる。
ア:地図とは、地球上の表面(地形や地物)を、「平面上」に投影して作成されたものである。
イ:地球の表面は、「曲面」である。
ウ:丸いボールに1枚の紙がピッタリと貼り付けられないように、地球の表面を全ての項目(角度や面積、長さ、方位)を正確に、平面上に表すことは「不可能」である。
エ:ウにあるような全ての項目を平面上に表そうとすると、どこかに「ひずみ」を生じる。
このため地図は、その利用目的に応じて特定の項目のみを正確に表すものや、全ての項目について「ひずみ」を極力小さくするように、作成されている。
オ:地図の投影では、「長さ」「角度」「面積」のひずみが、できるだけ小さくなるようにしている。
解答:5
|
|
|
|
<H17-6-B:問題>
次の文は、一般的な地図編集における転位の原則について述べたものである。間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.水準点は転位できる。
2.道路と市町村界が近接している場合は、道路を真位置に表示し、市町村界を転位する。
3.海岸線は、原則として転位しない。
4.一条河川と鉄道が近接している場合は、一条河川を真位置に表示し、鉄道を転位する。
5.鉄道と道路が近接して並行している場合は、鉄道を真位置に表示し、道路を転位する。
|
|
|
<H17-6-B:解答>
地図の編集作業における「転位」の原則について問うているものである。問題各文について見ると、次のようになる。
1.正しい。位置を表す「基準点」の転位は許されないが、水準点の転位は骨格となる人工地物(道路や鉄道など)と近接している場合など、転位することができる。
2.正しい。有形線と無形線では、有形線を優先する。有形線は道路や鉄道などの人工地物と河川や海岸線などの自然物があり、無形線とは、等高線や境界など実際に地上には存在しない線を言う。
3.正しい。河川などの有形線自然物は、転移することはできない。
4.正しい。有形線の自然物と人工地物では、人工地物を転移する。河川は実幅が7.5m以上の場合は、両岸の水涯線を描き(二条河川)、それ以下の場合は、一条線で描かれる。
5.間違い。重要度の同じ有形線の人工地物が近接している場合は、双方の中間を中心線として、真位置に表示する。
解答:5
|
|
|
|
<H17-6-C:問題>
図6-1は、国土地理院発行の 1/25,000 地形図(原寸大、一部を改変)の一部である。この図にある讐察署の建物の経緯度はいくらか。最も近いものを次の中から選べ。
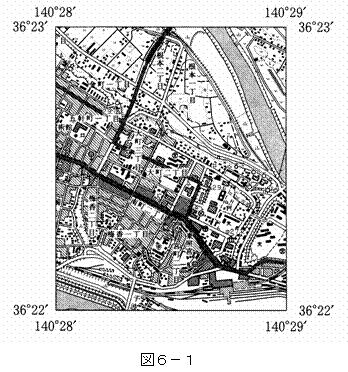
|
|
緯 度
|
経 度
|
|
1.
|
36°22′12″
|
140°28′27″
|
|
2.
|
36°22′25″
|
140°28′35″
|
|
3.
|
36°22′20″
|
140°28′36″
|
|
4.
|
36°22′09″
|
140°28′37″
|
|
5.
|
36°22′14″
|
140°28′45″
|
|
|
|
<H17-6-C:解答>
警察署の地図記号は、次図の通りである。これにより「警察署の建物」を判読し、経緯度の図郭線の長さを定規で測り、比例計算により求めればよい。
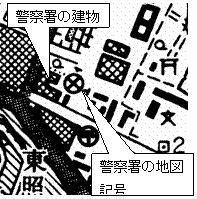
警察署の建物の位置を定規で測ると、次図のようになる。
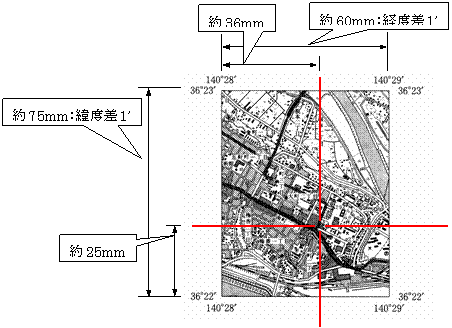
上図より、次のような比例式が組み立てられる。
<経度> 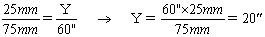
<緯度> 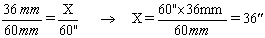
警察署の建物の経緯度は、図面左下の経緯度を基準に求めると、次のようになる。
・ 経度 → 36°22′+ 20″= 36°22′20″
・ 緯度 → 140°28′+ 36″= 140°28′36″
よって、正しい組合せは3となる。
解答:3
|
|
|
|
<H17-6-D:問題>
次の文は、地理情報を扱う際のベクタデータとラスタデータの特徴について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.スキャナを使用して直接得られるデータは、ベクタデータである。
2.ラスタデータを、ラスタ・ベクタ変換することにより、ベクタデータを作成することができる。
3.ベクタデータは、属性を付加して利用することが多い。
4.ベクタデータは、ディスプレイ上で任意に拡大や縮小しても、線の太さは変えずに表示することができる。
5.ラスタデータは、同一の対象について画素単位の大きさを小さくすると、データ量が増える。
|
|
|
<H17-6-D:解答>
1.間違い。スキャナを使用して直接得られるデータは、ラスタデータである。ベクタデータは、ディジタイザやCADなどを使用して得られるデータである。
2.正しい。スキャナにより得られたラスタデータは、ラスタ・ベクタ変換により、ベクタデータとして利用される。
3.正しい。ベクタデータは、図形に付随する属性(標高点の標高値や建物の階数など)を付加する。
4.正しい。ベクタデータは、端点に座標値を持ち、端点から端点への方向と量を持つベクトルデータである。また、ラスタデータは、ドット(画素)の集合体で表され、個々の点に座標値を持つ。このため、問題文にあるように、PC画面を拡大しても、その大きさ等が変化することはない。
5.正しい。ラスタデータは、ドット(画素)の集合体である。ディジタルカメラやスキャナなどは、その画像単位をいくつのドットであらわすかによって、解像度(画像を現す精密さ)が決定される。問題文のように、画素単位の大きさを小さくすると、解像度は上がるが、データ量は増加することになる。
解答:1
|
|
|
|
(c)Matsubara.P.O & (c) Sey Q’xara |