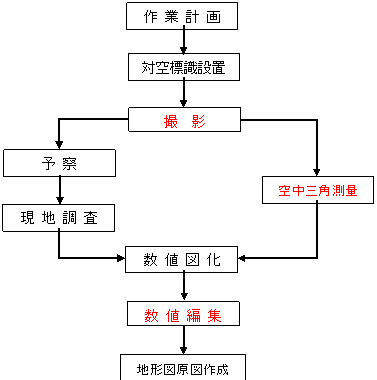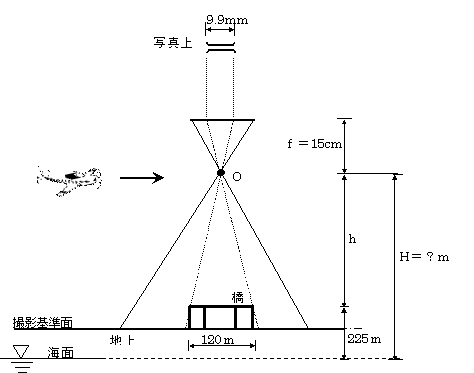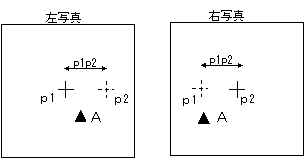| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<H20-5-A:解答>
● 関連問題(写真測量の作業工程) No5(写真測量):H17-C・H20-A(出題回数 2/15)
問題文の作業工程に適当な語句を当てはめると、次のようになる。 よって、適当な語句の組合せは、「1」となる。
解答:1
※参考までに公共測量作業規程による、写真測量による地図作成工程を以下に記す。
|
|
<H20-5-B:解答>
● 関連問題(写真測量作業全般) No5(写真測量):H20-B ※ 対空標識の設置 H6-A・H10-B・H11-D・H15-A
解答:4 |
|
<H20-5-C:解答>
● 関連問題(撮影高度と縮尺) No5(写真測量):H6-C・H7-B・H8-B・H9-A・H10-C・H13-B・H15-B・H18-B・H20-C (出題回数 9/15)
空中写真の撮影高度と縮尺の計算に関する問題である。問題文を図に描くと次のようになる。 よって、問題にある空中写真の海抜撮影高度は、2,043mとなり、最も近いものは、「1」の2,040mとなる。 ※撮影高度や海抜撮影高度の違いに注意する。
解答 1 |
|
<H20-5-D:解答>
● 関連問題(撮影基線長) No5(写真測量):H11-A・H12-B・H16-A・H17-A・H18-A・H19-C・H20-D(出題回数 7/15) 主点基線長から空中写真の重複(オーバーラップ:以下OL)を求める問題である。
まず、主点基線長の式 b = s(1−p) を変換して、
ここで、b:主点基線長(主点距離)s:写真画面の大きさ OL:オーバーラップ (重複度(%))
上式に問題文の数値を代入すると、次のようになる。
主点基線長とは、隣接する一組の空中写真を図のように、互いに移写した場合の主点間(p1p2)の平均値を言う。
よって、写真のOLは、78%となる。
解答 3 |