| H17年度 測量士補試験 No5 写真測量 |
|
|
<H17-5-A:問題>
画面距離15cm、画面の大きさ 23cm×23cm の航空カメラを用いて、海面からの高度 3,500m、
オーバーラップ60%で標高200mの平たんな土地の鉛直空中写真を撮影した。
このときの撮影基線長はいくらか。最も近いものを次の中から選べ。
|
1.
|
0.9km |
|
2.
|
1.0km |
|
3.
|
2.0km |
|
4.
|
2.3km |
|
5.
|
3.0km |
|
|
|
<H17-5-A:解答>
問題文にある撮影基線長は、以下の手順で求められる。
①1枚の写真に写る、地上の範囲(S)を求める。
写真縮尺は、画面距離と撮影高度より、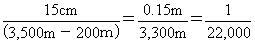 となる。 となる。
※問題文にある3,500mは「海抜高度」である。撮影高度は、撮影地点の標高200mを引いた、3,300mとなる。
画面の大きさが、23cm×23cmであるため、1枚の写真に写る地上の範囲は、
0.23m×22,000=5,060m(一辺)となる。
②撮影基線長(B)を求める。
撮影基線長(B)は、オーバーラップ(OL)と写真に写る地上の範囲(S)を用いて、次のように表される。
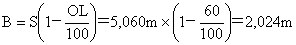
よって、撮影基線長は約2.0kmとなる。
解答:3
|
|
|
|
<H17-5-B:問題>
台風が過ぎ去った平たんな地域において、縮尺 1/20,000で鉛直空中写真を撮影した。写真上には、台風の影響を全く受けていない高塔と、横倒しになった樹木が写っている。高塔は写真上に長さ 2mmで写っており、鉛直点から高塔先端までの写真上の距離は10cmであった。また、樹木は、鉛直点に生えていたものが根元から折れて完全に横たわり、長さ 1mmで写っていた。高塔の高さと倒れた樹木の元の高さの関係について正しいものはどれか。最も近いものを次の中から選べ。
ただし、航空カメラの画面距離は15cmとする。
1.高塔は倒れた樹木の半分の高さである。
2.高塔は倒れた樹木と同じ高さである。
3.高塔は倒れた樹木の2倍の高さである。
4.高塔は倒れた樹木の3倍の高さである。
5.高塔は倒れた樹木の4倍の高さである。
|
|
|
<H17-5-B:解答>
この問題は次図のようになり、次の手順で求められる。
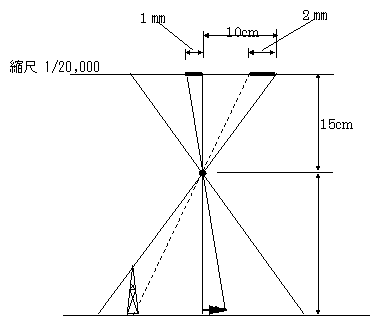
①撮影高度の計算
写真縮尺から撮影高度を計算すると、次のようになる。
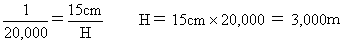
②高塔の高さを求める。
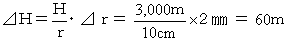
③倒木の高さを求める。
倒木の高さは、問題文より「鉛直点に生えていたものが、根元から折れて完全に横たわっている」ため、次のように、写真上の長さに、写真縮尺をかければその高さとなる。
1㎜ × 20,000 = 20m
よって、高塔は倒木の高さの3倍となる。
解答:4
|
|
|
|
<H17-5-C:問題>
図5-1は、ディジタルマッピング(DM)の主要な作業工程を示したものである。
ア ~ エ に入る作業名の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
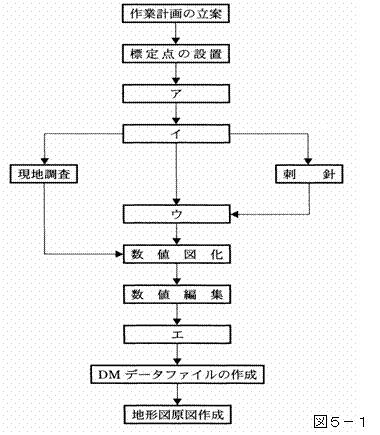
|
|
ア
|
イ
|
ウ
|
エ
|
|
1.
|
対空標識設置
|
撮 影
|
空中三角測量
|
現地補測
|
|
2.
|
撮 影
|
対空標識設置
|
計測用基図の作成
|
現地補測
|
|
3.
|
対空標識設置
|
撮 影
|
計測用基図の作成
|
地形図数値化
|
|
4.
|
対空標識設置
|
撮 影
|
空中三角測量
|
地形図数値化
|
|
5.
|
撮 影
|
対空標識設置
|
空中三角測量
|
地形図数値化
|
|
|
|
<H17-5-C:解答>
ディジタルマッピングの作業工程は次の通りである。
また、ディジタルマッピングは空中写真測量の図化の段階で、ディジタルデータを取得(作成)するため、数値図化までの作業工程は、空中写真測量と同様である。
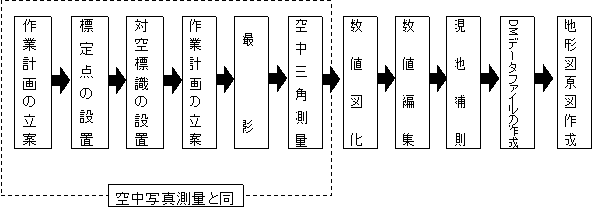
解答:1
|
|
|
|
<H17-5-D:問題>
図5-2は、オーバーラップ60%で撮影された一組の鉛直空中写真を縦視差のない状態に置いたものである。地上の目標物 A ~ E が左右の写真に図5-2のように写っていたとき、地上で最も高いものはどれか。次の中から選べ。なお、写真中央の破線の交点は主点を示している。
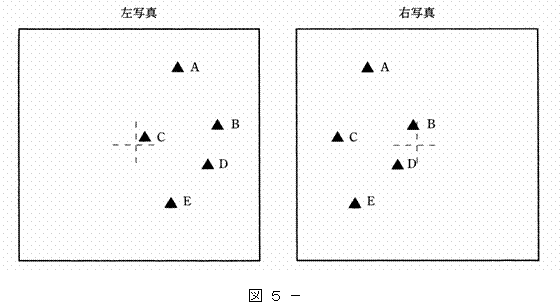
|
|
|
<H17-5-D:解答>
問題文の図5-2は、縦視差がない状態であるため、「裸眼実体視」を行ってみるとE点が一番高いことが分かる。
また、実体視が困難な場合は、下図のように、左右写真上の対応する2点間の長さを測り、一番短い点が最も高い点であると言える。
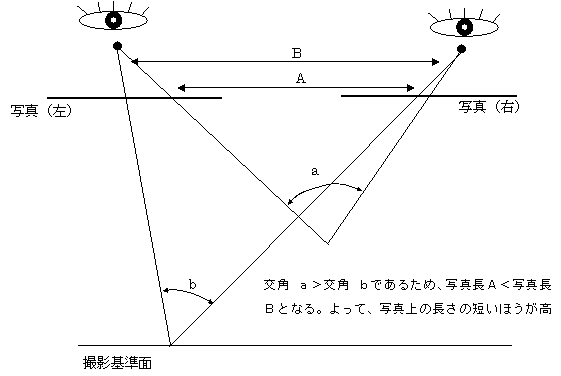
解答 5
※裸眼実体視では、本来「左目で左の画像」、「右目で右の画像」を見るが、人により逆の画像を見てしまう、「逆実体視」が起こることがある。逆実体視では、高低が逆に見えるため、裸眼実体視が困難となるが、2枚の画像中央に紙などで作成した「ついたて」を立てる事により、矯正が可能である。勿論、実体視がなかなかできない場合も上記方法により、訓練することができる。
|
|
|
|
(c) Matsubara.P.O & (c) Sey Q’xara |