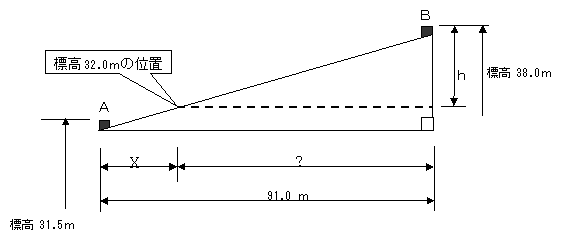| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<H20-4-A:解答>
● 関連問題(アーク・ノードデータ構造) No4(地形測量):H11-D・H13-D・H16-D・H19-C・H20-A(出題回数 5/15)
GISに主に用いられるベクタデータの形式(アーク・ノードデータ構造)に関する問題である。 このデータ形式は、点情報、線情報、面情報をそれぞれ、ノード、チェーン、ポリゴンの関係で表しているものであり、それぞれのデータには、属性情報と呼ばれる、点(線、面)番号や、座標データなどが、階層形式により付属している。
以下に、問題文の表を用いて記す。
よって、必要な属性情報の組合せは、「2」の「ア、エ、オ、カ、ケ」となる。
解答:2 |
|
<H20-4-B:解答>
● 関連問題(GPS測量の特徴) No4(地形測量):H20-B (出題回数 1/15) No4(地形測量):H6-D・H7-D・H8-D・H9-C・H10-D・H11-C・H12-D・H13-C・H14-C・H17-D・H18-C ※GPSとTSを用いた地形測量で、GPSは選択肢の一部として掲載される事がある。 No2(多角測量):H6-D・H7-A・H8-D・H12-D・H17-D・H18-D ※GPSを用いた基準点測量にて出題
GPS測量の特徴に関する問題である。問題文にRTK-GPSとあるため、面食らうかもしれないが、 RTK-GPSに関する選択肢(語句)は1箇所だけであり、その他はGPS測量に関する特徴をしっかりとつかんでおけば解答できる。
問題文のア〜オに適当な語句を記すと次のようになる。
RTK-GPS測量では、 天候 の影響にもほとんど左右されずに観測を行うことができ、既知点(基準局)と測点間の 視通 が確保されていなくても観測は可能である。また、省電力無線機や携帯電話を利用して観測データを送受信することにより、 基線解析 がリアルタイムに行えるため、現地において地形・地物の相対位置を算出することができる。地形・地物の観測は、放射法により1セット行い、観測に使用する人工衛星数は 5衛星 ※ 以上使用しなければならない。また、人工衛星からの電波を利用するため 上空視界 の確保が必要となる。
よって、正しい語句の組合せは、「5」となる。
解答:5 RTK-GPSとは、基準点(固定点)と観測点(移動点)で同時に観測し、基準点で観測したデータを無線機等を利用して観測点に送る事により、GPS測量機の内部で基線解析がリアルタイム(1秒ごと)で行え、観測点で高精度の三次元情報(位置情報)が得られる測量手法である。 |
|
<H20-4-C:解答>
● 関連問題(TSを用いた細部測量) No4(地形測量):H8-B・H15-C・H16-C・H17-C・H19-A・H20-C (出題回数 6/15)
TS等により取得されたデータは数値データであり、これら数値を眺めてみても現地の状況は到底理解できない。このため、後の編集作業や確認作業に用いるため、細部測量では、地形、地物等の測定を行うほか、編集及び編集した図形の点検に必要な資料(測定位置確認資料※)を現地にて作成する必要がある。 TSの特性は、角度(方向)と距離が同時に観測できることである。放射法は、方向線とその距離によって地物の位置を求める方法であるため、TSの特性を最大限に活かし、効率よく観測作業を行う事ができる方法であると言える。このため、主として放射法を用いるのが良く、その他に支距法、前方交会法や、他の有効な測定法を用いることができる。 現地補測(現地補備測量)とは、注記や境界等の重要な表現事項で再確認が必要なものや、現地調査以降に生じた変化に関する事項、各種表現対象物の表現の誤りや脱落などに関して、現地で調査、確認、測量するものである。TSを用いた地形測量では、主にオフライン方式の場合に行われ、基準点やTS点など編集過程において明瞭な点に基づいて行なわれる。 TS点とは、地物や地形など地上の状況に応じて、基準点からの地形細部測量が困難な場合に設置される補助基準点を言う。TS点は、基準点からの「放射法」 又はTS点にTSを整置して「後方交会法」により設置することができる。
解答:3 |
|
<H20-4-D:解答>
● 関連問題(等高線測定) No4(地形測量):H13-B・H18-A・H20-D(出題回数 3/15)
ここで、点A〜Bを結ぶ線上でA点に最も近い等高線は32.0mであるため、三角形の相似より、次の比例式が組み立てられる。 6.5m : 6.0m = 91m : ? これを解くと、ℓ = 84.0m となり、A点から、 X = 91.0m − 87.0m = 6.0m の位置に標高32.0mの等高線があると言える。 ※ここで、A〜B間の高低差は、6.5m 標高32.0mの等高線からB点までの高低差hは6.0m
解答:1 |