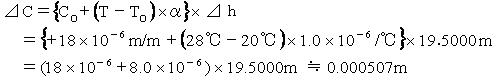| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<H20-3-AپF‰ً“ڑ>
پœپ@ٹضکA–â‘èپiƒŒƒxƒ‹‚ة‚و‚éٹد‘ھچى‹ئ‚ج’چˆسژ–چ€پj No3پiگ…ڈ€‘ھ—تپjپFH6-AپEH7-AپEH8-AپEH9-CپEH10-DپEH11-CپEH17-A¥H18-A¥H19-A¥H20-A پiڈo‘è‰ٌگ”پ@11پ^15پj پ@ƒŒƒxƒ‹‚ة‚و‚éٹد‘ھچى‹ئ‚ج’چˆسژ–چ€‚ةٹض‚·‚é–â‘è‚إ‚ ‚éپBˆب‰؛‚ةپA–â‘蕶’†‚جٹe‘I‘ًژˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‰ًگà‚·‚éپB
‰ً“ڑپF‚T
|
|
<H20-3-BپF‰ً“ڑ>
پœپ@ٹضکA–â‘èپi“dژqƒŒƒxƒ‹پj No3پiگ…ڈ€‘ھ—تپjپFH11-AپEH13-DپEH20-Bپ@پiڈo‘è‰ٌگ”پ@3پ^15پj
‰ً“ڑپF‚R |
|
<H20-3-CپF‰ً“ڑ>
پœپ@ٹضکA–â‘èپi•Wژع•âگ³پj No3پiگ…ڈ€‘ھ—تپjپFH16-DپEH20-Cپiڈo‘è‰ٌگ”پ@2پ^15پj
•Wژع•âگ³‚ةٹض‚·‚éŒvژZ–â‘è‚إ‚ ‚éپB
•Wژع•âگ³‚حˆب‰؛‚جژ®‚ة‚و‚èچs‚ي‚ê‚éپBپi•Wژع•âگ³ŒvژZپj
‡™‚bپF•Wژع•âگ³—ت ‚b‚OپFٹîڈ€‰·“x‚ة‚¨‚¯‚é•Wژع’èگ” ‚sپFٹد‘ھژ‚ج‘ھ’艷“x ‚s‚OپFٹîڈ€‰·“xپi•Wژع’èگ”‚جٹîڈ€‰·“xپj ƒ؟پF–c’£ŒWگ” ‡™‚ˆپFچ‚’لچ·
‘Oژ®‚ة–â‘è‚جگ”’l‚ً“–‚ؤ‚ح‚ك‚é‚ئژں‚ج‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ¦ 18ƒتmپiƒ}ƒCƒNƒچƒپپ[ƒgƒ‹پj‚حپA18پ~10پ|6m‚إپA1پ^1,000,000 m‚جژ–‚إ‚ ‚éپB
‚و‚ء‚ؤپA•âگ³Œم‚جچ‚’لچ·‚حژں‚ج‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ|پb19.5000mپ{0.000507mپbپپپ| 19.500507m
‚و‚ء‚ؤپAچإ‚à‹ك‚¢’l‚حپAپu‚Sپv‚ج پ|19.5005‚چ ‚ئ‚ب‚éپB
‰ً“ڑپF‚S |
|
<H20-3-DپF‰ً“ڑ>
پœپ@ٹضکA–â‘èپi‚‚¢‘إ‚؟’²گ®–@پj No3پiگ…ڈ€‘ھ—تپjپFH7-BپEH8-BپEH10-BپEH12-AپEH13-AپEH15-BپEH16-AپEH17-BپEH18-BپEH19-BپEH20-C پiڈo‘è‰ٌگ”پ@11پ^15پj پ@‚‚¢‘إ‚؟’²گ®–@‚جŒvژZ–â‘è‚إ‚ ‚éپB
‰ً“ڑپF‚S |