| H17年度 測量士補試験 No3 水準測量 |
|
|
<H17-3-A:問題>
次の文は、水準測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.精密な水準測量では、標尺補正のために温度を測定する必要がある。
2.器械及び標尺は、点検、調整されたものを使用する。
3.チルチングレベルを用いて観測する際には、気泡を合致させる。
4.新設点の観測は、永久標識の埋設後ただちに行う。
5.手簿に記入した読定値及び水準測量用電卓に入力した観測データは、訂正してはならない。
|
|
|
<H17-3-A:解答>
問題各文について見ると、次のようになる。
1.正しい。精密な水準測量(1・2級)では、標尺目盛の補正を行うため、観測の開始時と終了時また、観測点及び固定点への到着時に、温度を1℃単位で測る必要がある。
2.正しい。観測に使用する器械は、観測着手前や観測期間中に適宜点検及び調整する。
3.正しい。チルチングレベルは、気泡管レベルとも呼ばれ、気泡管水準器を合致させ、レベルの視準線を水平にする必要がある。この操作を自動化したものが、オート(自動)レベルと呼ばれるものである。ちなみに、レベルを据付けるために使用する気泡管は、「円形(型)水準器」と言う。
4.間違い。新点の観測は、埋設された永久標識が沈下等の影響がなく、安定した状態になってから行う必要がある。作業規程では、埋設後1週間以上が望ましく、やむを得ない場合でも24時間経過してから観測すると規定されている。
5.正しい。記帳された(入力した)観測データは、観測作業に作為がなく、その信頼性を高めるためにも、訂正をしてはいけない。誤記や再測による場合は、その測点の観測をやり直し、その結果を記入する必要がある。
解答:4
|
|
|
|
<H17-3-B:問題>
レベルの視準線を点検するために、図3-1に示す観測を行い、表3-1の結果を得た。レベルの視準線を調整したとき、レベルの位置Bにおける標尺Ⅱの読定値はいくらになるか。次の中から選べ。ただし、読定誤差はないものとする。

|
表3-2
|
|
レベル
の位置
|
読定値
|
|
Ⅰ
|
Ⅱ
|
|
A
|
1.002m
|
1.123m
|
|
B
|
1.084m
|
1.225m
|
|
1.
|
1.203m
|
|
2.
|
1.205m
|
|
3.
|
1.225m
|
|
4.
|
1.245m
|
|
5.
|
1.247m
|
|
|
|
<H17-3-B:解答>
レベルの視準線の点検調整(杭打ち調整法)に関する問題である。計算手順を次に記す。
①A、Bそれぞれのレベル位置における2点間(Ⅰ、Ⅱ)の高低差を計算する。
レベル位置A:1.002m - 1.123m = -0.121m
レベル位置B:1.084m - 1.225m = -0.141m
ここで、レベル位置Aの観測結果はレベルと前後標尺の間隔が等しいため、視準線誤差が消去された高低差であると言える。
②補正量の目安を付ける。
レベル位置Bの高低差は視準線誤差を含んだものであり、その大きさは、
-0.121m-(-0.141m)= 0.020m である。
これにより、レベル位置Bにおいて視準線誤差を消去しようとすれば、0.020m低い、標尺Ⅱの 1.225m - 0.020m = 1.205m 付近を見ればよいと言える。
※選択肢中に、1.205m があるが、これが正答ではない。
③レベル十字線の調整後の標尺読定値の計算
レベル十字線の調整量は、比例式により次のように計算される。
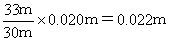
よって、レベル位置Bにおける視準線調整後の標尺Ⅱの読定値は、次のようになる。
1.225m - 0.022m = 1.203m
解答:1
|
|
|
|
<H17-3-C:問題>
次の文は、水準測量における誤差を消去あるいは小さくするための方法について述べたものである。望遠鏡の視準軸と気泡管軸が平行でないために生じる誤差(視準軸誤差)の消去法について述べたものはどれか。次の中から選べ。
1.水準点間のレベルの整置回数を偶数回にする。
2.レベルと標尺の前視、後視の距離が等しくなるように整置し、観測する。
3.標尺の地表面に近い部分の視準を避ける。
4.レベルの望遠鏡と三脚の向きを、特定の標尺に対向させて整置し、観測する。
5.地盤堅固な場所にレベルを整置し、観測する。
|
|
|
<H17-3-C:解答>
問題各文について見ると、次のようになる。
1.標尺の「零」点誤差の消去法
2.視準軸誤差の消去法
3.大気の屈折による誤差(気差)の軽減法
4.鉛直軸誤差の軽減法
5.レベルの沈下による誤差の軽減法
よって問題文にある、「視準軸誤差の消去法」を記しているのは、2である。
解答:2
|
|
|
|
<H17-3-D:問題>
図3-2に示す水準路線で交点1を再設するため、周囲の既設水準点A、B、Cからそれぞれ水準測量を行い、表3-2の結果を得た。交点1の標高の最確値はいくらか。次の中から選べ。
ただし、既設水準点A、B、Cの標高は、それぞれHA=26.984m、HB=40.256m、
HC=48.942mとする。また、表3-2及び図3-2中の矢印は、観測高低差を得た方向を表す。
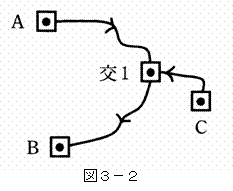
| 表3-2 |
| 路 線 |
距 離 |
観測高低差 |
| A → 交1 |
4km |
+ 9.557m |
| 交1 → B |
4km |
+ 3.725m |
| C → 交1 |
1km |
-12.385m |
|
1.
|
36.540m
|
|
2.
|
36.543m
|
|
3.
|
36.547m
|
|
4.
|
36.550m
|
|
5.
|
36.553m
|
|
|
|
<H17-3-D:解答>
交点1の標高の最確値は、次のように計算される。
|
路 線
|
距 離
|
観測高低差
|
標 高
|
|
A → 交1
|
4km
|
+ 9.557m
|
26.984m + 9.557m = 36.541m
|
|
交1 → B
|
4km
|
+ 3.725m
|
40.256m - 3.725m = 36.531m
|
|
C → 交1
|
1km
|
-12.385m
|
48.942m - 12.385m = 36.557m
|
① 各路線における交点1の標高の計算
※路線の向き(→)に注意する
② 各路線の重量(重み)を求める。
各路線の重量は、「観測距離に反比例する」ため、次のようになる。
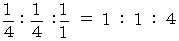
③ 重量計算により、交点1の標高の最確値を求める。
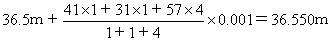
解答:4
|
|
|
|
c Matsubara.P.O & c Sey Q’xara |