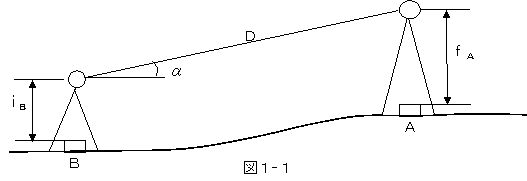| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
次の文は、スタティック法によるGPS測量について述べたものである。 明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.GPS測量では、通常、気温や気圧の気象観測は行わない。 2.GPS測量では、短距離基線の観測には1周波GPS受信機を通常使用する。 3.GPS測量の基線解析を実施するために、衛星の軌道情報は必要ない。 4.GPS測量では、複数の観測点においてGPS衛星を同時に4個以上使用することができれば、基線解折を行うことができる。 5.GPS測量の基線解析で用いられる観測点の高さは、楕円体高である。 |
|
<H18-1-A:解答>
GPS測量の概論についての問題である。問題各文について考えると、次のようになる。
1.正しい。 2.正しい。 3.間違い。 4.正しい。 5.正しい。
解答:3 |
|
<H18-1-B:問題>
公共測量において、トータルステーションを用いて実施する基準点測量の作業順序として最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
|
|
<H18-1-B:解答>
TSによる基準点測量の、現地作業の順序に関する問題である。
通常の作業工程は次のようである。 踏査及び選点 → 測量標の設置(埋標) → 測量機器の点検 → 観 測 → 標高の概算 → 座標の概算
解答:5 |
|
<H18-1-C:問題>
新点Aの標高を求めるため、図1-1のとおり既知点Bから新点Aに対して高低角α及び斜距離Dの観測を行い、表1-1の結果を得た。新点Aの標高はいくらか。最も近いも のを次の中から選べ。 ただし、既知点 Bの標高は330.00m、両差は0.15mとする。また、斜距離Dは気象補正、器械定数補正及び反射鏡定数補正が行われているものとする。なお、関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。
|
|
<H18-1-C:解答>
三角水準測量に関する計算問題である。
HA =HB + Dsinα +iB -fA + K = 330.00m + 130.74m + 1.50m - 1.80m + 0.15m = 460.59m
※Dsinα = 1,500.00m × sin 5°= 1,500.00m × 0.08716(関数表より) ※ 両差の符号は、既知点BにTSを据付けて観測しているため「正方向の観測」であり、+となる。
解答:3 |
|
<H18-1-D:問題>
次の文は、セオドライト(トランシット)を用いた水平角観測において生じる誤差について、それぞれ述べたものである。望遠鏡の正(右)・反(左)の観測値を平均することで消去できる誤差の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
a.望遠鏡の視準線が、セオドライトの鉛直軸の中心から外れているために生じる誤差 b.セオドライトの水平目盛盤の目盛間隔が、均一でないために生じる誤差 c.空気密度の不均一さによる目標像のゆらぎのために生じる誤差 d.セオドライトの水平目盛盤の中心が、鉛直軸の中心と一致していないために生じる誤差 e.セオドライトの鉛直軸の方向が、鉛直線の方向に一致していないために生じる誤差 f.セオドライトの水平軸と鉛直軸が直交していないために生じる誤差
|
|
<H18-1-D:解答>
トランシットの誤差に関する問題である。問題文にある各誤差について考えると、次のようになる。
a.視準線誤差なので、正反の平均によって消去可能。 b.目盛盤誤差なので、目盛の全周を満遍なく使う観測方法で低減することが可能。 c.陽炎などの現象は観測時刻を吟味して観測するしかない。 d.目盛盤の偏心誤差は、正反の平均によって消去可能。 e.鉛直軸誤差なので、観測方向ごとの気泡管のずれを記録しておいた後、補正値を算出することにより、低減することが可能。 f.水平軸の誤差なので、正反の平均によって消去可能。
よって、正反の平均によって消去が可能なものは、a.d.f の組合せとなる。
解答:2 |