| H17年度 測量士補試験 No1 三角測量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-A:問題>
次の文は、GPS測量機を用いた測量について述べたものである。明らかに間違っている ものはどれか。次の中から選べ。
1.GPS衛星の飛来情報を事前に把握し、作業地域上空における衛星配置が片寄った状態での観測は避ける。 2.測量によって直接的に求められる高さは、標高である。 3.長距離基線の場合に2周波での観測を行うのは、電離層の影響を補正するためである。 4.観測点間の視通がなくても観測点間の距離と方向を求めることができる。 5.セオドライト(トランシット)や光波測距儀による測量に比べ、天候障害による影響は小さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-A:解答>
問題各文について考えると、次のようになる。
1.正しい。GPS衛星の配置が悪い場合、観測精度は低下する。GPS衛星の配置は、衛星同士を結んでできる、四面体の体積が最大となる場合に一番精度が良くなる。受信機では、DOPの数値で表されている。 2.間違い。GPS測量によって直接的に得られる、「高さ」のデータは、楕円体高である。「標高」とはジオイド面からの高さである。 3.正しい。基線長が10km以上になれば、電離層等の影響により衛星からの電波が遅れ計測精度が落ちるため、2周波(L1とL2)観測を行い、電離層遅延補正を行っている。GPS測量機は、2周波を同時に受信できるものを1級、1周波のみ受信できるものを2級GPS測量機としている。 4.正しい。GPS測量に測点間の見通しは不要。上空視界があればよい。 5.正しい。問題文のように、GPS測量は天候障害(雨や風)の影響は受けにくい。
解答:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-B:問題> 図1-1は標準的な基準点測量の作業工程を示したものである。 ア ~ オ に入る作業名の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。 ただし、a.測量標の設置 b.平均計算 c.踏査・選点 d.測量標設置承諾 e.現地における点検計算 とする。
作業計画・準備 → 関係官署への手続き及び敷地所有者への立ち入り連絡 → ア → イ → ウ → 観測使用機器の点検 → 観 測 → エ → オ → 成果表の整理 <図1-1>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-B:解答>
基準点測量の作業工程は次の通り。
① 計画(平均計画図・作業計画書の作成と提出)→ 計画機関(発注者側)が作成。 ② 選点(既知点の現況調査・現況調査報告書の作成・新点の選定・建標承諾書の取得・選点図及び平均図の作成) ③測量標の設置(埋標)(点の記の作成) ④ 観測(機器の点検・観測の実施・観測図・観測手簿の作成) ⑤点検(現地)計算(点検計算簿・精度管理表の作成) ⑥平均計算(計算簿・精度管理表の作成・成果等の作成) ⑦成果等の整理 ⑧納品
よって、選択肢「2」の流れが正しい。
解答:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-C:問題>
基準点測量において、A点からB点及びC点への視通が確保できないため、図1-2のように、A点に偏心点Pを設けて観測を行い、表1-1の結果を得た。このとき∠BACの値として最も近いのはどれか。次の中から選べ。 ただし、計算においてBA=BP、CA=CPとする。また、ρ"=2"×105とする。なお、関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。
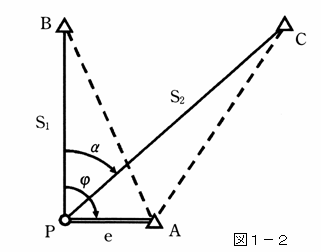
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-C:解答>
問題文の図に、ABと平行に、またACと平行に、図のような線を引くと理解しやすい。
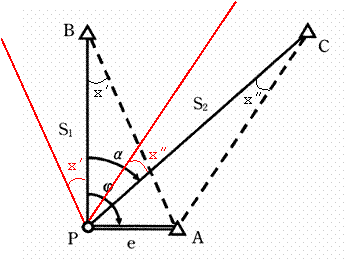 図より、求める角度 ∠BAC=α-x″+x′であることがわかる。 よって、偏心補正角x′、x″を求めると、次のようになる。
※ ∠CPA=φ-α = 30° また、問題文より CP=CA のため。
よって、∠BAC = 60°0′0″- 50″+ 200″= 60°2′30″ となる。
解答:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-D:問題>
次の文は、基準点測量の踏査・選点における留意点を述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.新点の設置位置は、周囲の見通しがよく、利用しやすく、かつ保全に適した場所を選ぶ。 2.新点の配置は、既知点を考慮に入れた上で、配点密度が必要十分でかつできるだけ均等になるようにする。 3.新点の設置位置は、地盤の堅固な場所を選ぶ。 4.GPS測量機を用いた測量の場合は、レーダーや通信局などの電波発信源となる施設付近は避ける。 5.トータルステーションを用いた測量の場合は、できるだけ一辺の長さを短くして、節点を多くする |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<H17-1-D:解答>
問題文について見ると、次のようになる。
1.~ 4.正しい。問題文の通り。 5.間違い。節点とは、障害物等により隣接する基準点間の見通しがない場合に、やむをえず設けられる仮設の観測点(中継ぎ点)である。 このため、精度の問題からも、節点数(路線の辺数)はなるべく少なく、その距離も等しくする必要がある。公共測量作業規定では、基準点測量の区分(1級~4級)において、節点間の(最低)距離が決められている。
解答:5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Matsubara.P.O & c Sey Q’xara |