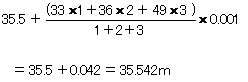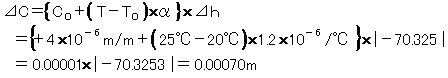| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<No9:水準測量:解答>
水準測量の誤差に関する問題である。各選択肢について考えると次のようになる。
よって、正しい語句の組合せは、1となる。
解答: 1 |
|
<No10:水準測量:解答>
水準測量における観測作業の注意点に関する問題である。各選択肢について考えると次のようになる。
よって、明らかに間違っているのは、dの1つだけとなる。
解答: 2 |
|
<No11:水準測量:解答>
重量平均による最確値の計算問題である。次の手順で解答すればよい。
かけて整数にしている。 ※重量は分数のまま計算しても良い。
よって、最も近い選択肢は4の35.542mとなる。
解答: 4 |
|
<No12:水準測量:解答>
標尺補正計算に関する問題である。標尺補正計算とは、あらかじめ観測に使用する標尺を基準尺により点検して長さの補正値を求めておき、観測値に対して補正を行うもので、次式により計算される。
問題文において、標尺補正の計算を行なうと次のようになる。
T0:基準温度(標尺定数の基準温度) α:膨張係数 ⊿h:高低差(往復観測の平均値)
|-70.3253m| + 0.00070m =-70.3260m
解答: 2 |