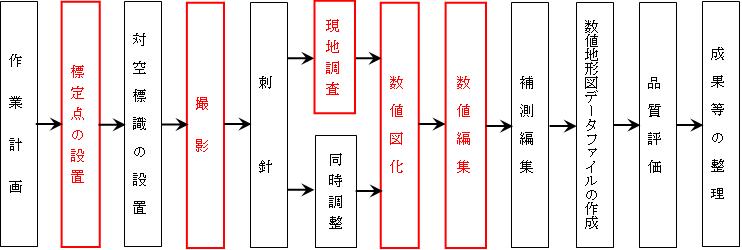| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
��No16�F�ʐ^�F�� �ʐ^���ʂ̍�ƍH���Ɋւ�����ł���B��蕶�̍�ƍH�������̂܂܊o���Ă��܂��悢�B ���ӂ��ׂ��́A�ȑO���炠�����u�O�p���ʁv�̋L�ڂ������Ȃ�A�u���������v�ƂȂ������ł���B
���u�O�p���ʁv���u���������v�ƂȂ����̂́AGNSS/IMU���u��p���A�B�e�Ɠ����ɋʐ^�̎B�e�ʒu�ƌX���i������O���W��v�f�j���v�����鎖���\�ɂȂ������߂ł���B ��ƋK���̏����ɂ��A�u���������v�̓f�W�^���X�e���I�}���@��p���āA�O�p���ʂɂ��A�p�X�|�C���g�A�^�C�|�C���g�A�W��_�̎ʐ^���W�𑪒肵�A�W��_���ʋy�юB�e���ɓ���ꂽ�O���W��v�f�����Ē����v�Z���s���A�e�ʐ^�̊O���W��v�f�̐��ʒl�A�p�X�|�C���g�A�^�C�|�C���g���̐����ʒu�y�ѕW�������肷���Ƃ������B�i157���j�Ƃ���B ����ɂ��A�]������̋O�p���ʂ��A�O���W��v�f�̎Z�o���Ԃ��傫���Z�k�����悤�ɂȂ����B���s�̍�ƋK���̏���������u�O�p���ʁv�̐߂͍폜����Ă���B |
|
��No17�F�ʐ^�F�� �@�p�X�|�C���g�ƃ^�C�|�C���g�Ɋւ���o��ł���B�I������H19�AH22�Ƃقړ����ł������B �@����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂͂S�ł���B �F�@�S |
|
��No18�F�ʐ^�F�� �@�f�W�^���X�e���I�}���@�̓����Ɋւ�����ł���B���e���ɂčl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�F�@�Q |
|
��No19�F�ʐ^�F��
�P�D1��f�̃T�C�Y���A6�ʂ��ł��邽�߁A�n���f���@��18�p�̏ꍇ�A�ʐ^�k�ڂ͎��̂悤�ɂȂ�B �@
�� 1�ʂ��́A0.000001���i1�~10�|�U�j�ł���B �Q�D��ʋ�����7�p�ł��邩��A���̋ʐ^�̎B�e���x�́A���̂悤�ɂȂ�B
�@����āA��蕶���B�e��ʂ��W��0���ł��邽�߁A���̋ʐ^�̎B�e���x�́A2,100���ł���B �F�@�S |
|
��No20�F�ʐ^�F��
�����ŁA�C���B�e���x�ƑΒn���x�̊W�ɒ��ӂ���K�v������B��蕶�́A���̎��������߂Ă��邽�߁A�ʐ^�k�ڂ��C���B�e���x����B�e���ꂽ���̕W�������������̂�p���Ă���B �Q�D��f���@����ʐ^��̋��̒��������߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B ��1�ʂ��́A0.000001���i1�~10�|�U�j�ł���B
�R�D�ʐ^�k�ڂ��狴�̎��������߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �@�@ �F�@�P |