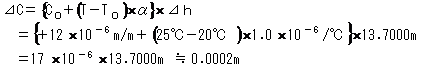| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<No9:水準測量:解答>
レベルと標尺の誤差に関する問題である。水準測量における定番問題であるため、誤差の「名前」、「内容」、「消去法」を確実に覚える必要がある。以下に、問題文中のア~オについて解説する。
解答: 3 |
|
<No10:水準測量:解答> 標尺補正計算に関する問題である。これは、あらかじめ観測に使用する標尺を基準尺により点検し長さの補正値を求めておき、観測値に対して補正を行うもので、次式により計算される。
問題文において、標尺補正の計算を行なうと次のようになる。
※ 12μm(マイクロメートル)は、12×10-6mで、12/1,000,000 mの事である。
よって、補正後の高低差は次のようになる。
+|13.7000m+0.0002m|=+13.7002m ※ 高低差の絶対値に対して計算を行う。
解答: 5 |
|
<No11:水準測量:解答>
レベルによる観測作業の注意事項に関する問題である。水準測量における定番問題であるため、よく理解しておく必要がある。また、まとめて出題される事もあるため、「観測作業の注意事項」と「誤差と消去法」はセットで覚える必要がある。以下に、問題文中の各選択肢について解説する。
解答:2 |
|
<No12:水準測量:解答>
レベルのくい打ち調整法(レベルの気泡管軸と視準軸(線)が平行(水平)であるかどうかの点検方法)に関する計算問題である。杭打ち調整法の原理はやや理解しがたいものではあるが、その出題形式は例年同じであるため、解答手法(計算の流れ)を身につけてしまった方が良い。 以下に、計算の流れに沿って解答する。
1.1987 m - 1.1506 m = 0.0481 m
1.2765 m - 1.2107 m = 0.0658 m
ここでレベルの視準線が水平ならば、 ① = ②であるが、①- ② = 0.0481 m - 0.0658 m = -0.0177 m であるため、視準線の調整が必要となる。 また、視準線が正確であると仮定するならば、レベル位置Bからの観測では、標尺Ⅰの読定値は 1.2765 m - 0.0177 m = 1.2588 m 付近であると言える。 ※ 1.2588 mが調整値ではない。 ④ 標尺Ⅰの調整量を求める。 レベルBにおける標尺Ⅰの調整量は、 従ってレベルBから、標尺Ⅰの読定値が 1.2765 m - 0.01947 m = 1.25703 m となるように、視準線を調整すればよい。
よって、最も近い標尺Ⅰの読定値は、1の1.2570 mとなる。
解答:1 |