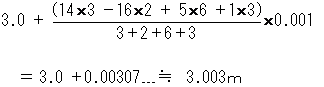| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<No9 :水準測量:解答>
重量平均による標高の最確値を求める問題である。水準測量分野における計算問題としては定番問題となる。以下に、計算手順を解説する。
かけて整数にしている。 ※重量は分数のまま計算しても良い。
よって、最も近い選択肢は4の3.003mとなる。
解答: 4 |
|
<No10:水準測量:解答>
電子レベルの特長に関する問題である。以下に、問題文中の各選択肢について解説する。 また、電子レベルに関しては、「レベルによる観測作業の注意事項」中で選択肢の一つとして出題されるケースが多い。
よって、明らかに間違っている文書は、4である。
解答: 4 |
|
<No11:水準測量:解答>
レベルによる観測作業の注意事項に関する問題である。定番問題であるため、観測作業の注意事項と誤差と消去法はセットで覚える必要がある。以下に、問題文中の各選択肢について解説する。
よって、明らかに間違っているのは、2となる。
解答: 2 |
|
<No12:水準測量:解答>
較差と許容範囲から、再測区間を求める計算問題である。この問題は、次の手順で解けばよい。
問題文より、各観測区間の区間距離は全て500mである。このため、各観測区間の較差の許容値は、m = 2.5mm×√0.5 = 2.5mm × 0.707 = 1.768mm ≒ 0.0017mとなる。 ※ 四捨五入の0.0018では、再測となるため0.0017としておく。
C) 較差の許容値と観測値の較差を比較し、再測すべき区間を求める B)の表より、較差の許容値を超えている区間は、③である。このため、③の区間が再測となる。
D) 念のため、往復それぞれの水準点間の較差を計算し誤差を求める B)の表より、往復の高低差から較差を求めると次のようになる。 -0.6949(往観測の高低差) +0.6932(復観測の高低差) = 0.0017m
E) 全体の路線長に対する較差の許容範囲を求めると、次のようになる。 2.5mm×√2.0km = 2.5mm × 1.4142 ≒ 3.2mm = 0.0035m
F) 再測の判定 D)とE)より、往復観測の較差が、許容範囲内であるため、路線全体では、再測の必要はない。
よって、再測が必要な区間は、3.の ③ となる。
解答: 3 |