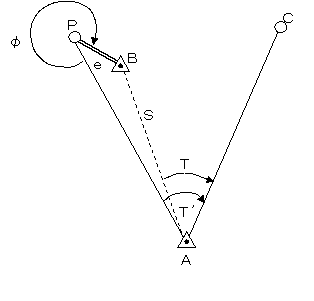| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
��No4�F��_���ʁF��
���@���@��
�@�ϑ��l�̕W���������߂���ł���B
�v�Z�̎菇�Ƃ��ẮA�����p�̍Ŋm�l�����߂Ă���W���������߂�悢�B
�@ �Ŋm�l�����߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �@ �A �e�ϑ��l�̎c�������߂�B
�@ �W���������߂�
�� �����ŁA�Ŋm�l�̕W�����ł��邽�߁A�W�����̎��ɒ��ӂ���B
����āA�́A�u�Q�v�ƂȂ�B
�F�Q |
|
��No5�F��_���ʁF��
�@GPS�@���p�������ʂ̓����Ɋւ�����ł���B �@��蕶�ɐ��������Ă͂߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
GPS���ʋ@��p�������ʂɂ������v�Ȍ덷�v���ɂ́AGPS�q���ʒu�⎞�v�Ȃǂ̌덷�ɉ����AGPS�q������ϑ��_�܂łɓd�g���`������ߒ��Ő�����덷������B���̂����A �@�d���w�x���덷�@�@ �͎��g���Ɉˑ����邽�߁A�Q���g�̊ϑ��ɂ��y�����邱�Ƃ��ł��邪�A �@�Η����x���덷�@ �͎��g���Ɉˑ������A�Q���g�̊ϑ��ɂ��y�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�����̓\�t�g�E�F�A�ō̗p���Ă���W���l��p���ċߎ��I�ɕ���s���� �@�l�b�g���[�N�^RTK-GPS�@ �@�ł́A���̂悤�Ȍ덷�ɑ��A��ǂ̊ϑ��f�[�^���������ʂȂǂ��擾���A��͏������s�����ƂŁA���̌y�����}���Ă���B �������AGPS�q�����璼�ړ��B����d�g�ȊO�ɓd�g���\�����Ȃǂɓ������Ĕ��˂������̂���M����錻�ۂł��� �@�}���`�p�X�@ �ɂ��덷�́A �@�l�b�g���[�N�^RTK-GPS�@ �@�ɂ���Ă���ł��Ȃ��̂ŁA�I�_�ɓ������ẮA���ӂɍ\�����������ꏊ��I�ԂȂǂ̒��ӂ��K�v�ł���B
�F�@�P
�d���w�x���덷�F�d���w�i�n��60�`100�q���x�Ɉʒu����ȑ�C�̑w���d����ԂɂȂ��Ă���̈�j��GPS�q������̓d�g���ʉ߂���ۂɁA���܂��d�g���B���Ԃ��x���Ȃ邽�߂ɐ�����덷�BGPS�q����L1�AL2�ƂQ�̓d�g�M���Ă���̂́A���̌덷�������i�y���j���邽�߂ł���B �܂��A�d���w�ł̓d�g�̋��ܗ��́A���g���̓��ɔ���Ⴗ��B
�Η����x���덷�F�Η����i�n��`10�q���x�܂ł̑�C�̑w�j��GPS�q������̓d�g���ʉ߂���ۂɐ����鑬�x�x���ɂ��덷�B��������邽�߂Ɋ����̓\�t�g�ɐݒ肳��Ă���f�t�H���g�l��p���ċC�ە���s����B
�l�b�g���[�N�^RTK-GPS���ʁFVRS�i���z��_�j�����ł́A�d���w��Η����̒x���A�q���̋O���덷������f�[�^�Ƃ��Ĕz�M���Ǝ҂���z�M����AFKP�i�ʕ�p�����[�^�j�����ł́A��ǂ̊ϑ�����d���w���̏�ԋ�ԃ��f�������A���̃��f�����������v�Z���邽�߁A�덷���y�������B |
|
��No6�F��_���ʁF��
�@�ΐS��v�Z�i�����藝�j�̌v�Z���ł���B ��蕶���A�����p�s���s�L�|�ڂo�`�a�i���j�ł��邱�Ƃ��킩��B�ڂo�`�a�����߂�ɂ́A�ȉ��̎菇�ʼn����čs���悢�B
�@�@ �ΐS��v�Z�ɂ��A�ΐS����I��( �ڂo�`�a)�����߂�B �@ �����ŁAsin330����360���|330���Ƃ��āAsin30���Ŋ��\�ɂ�肻�̒l�����߂�悢�B
�A�@�s���s�L�|�ڂo�`�a�@�ɂ�苁�߂�B �@ �s�� 53��25��23���| 100���� 53��23��43��
�@����āA�����p�s�́A�S �ƂȂ�B
�F�S |
|
��No7�F��_���ʁF��
�g�[�^���X�e�[�V����(�ȉ��s�r)�ƃf�[�^�R���N�^�i�ȉ��c�b�j�̓����Ɋւ�����ł���B��N�Ɉ��������Ă̏o��ƂȂ����B �ȉ��ɁA�e�I�����ɂ��ĉ������B
����āA���炩�ɊԈ���Ă���I�����́A�R�ł���B
�F�@�R |
|
��No8�F��_���ʁF��
�@GPS���ʋ@��p������_���ʂɊւ�����ł��邪�AGPS�Ɋւ���ƌ������́A��ƍH���Ɋւ�����e�̕����Z�����ł���B �ȉ��ɁA���e���ɂ��ĉ������B
����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂́A�S�ƂȂ�B
�F�@�S |