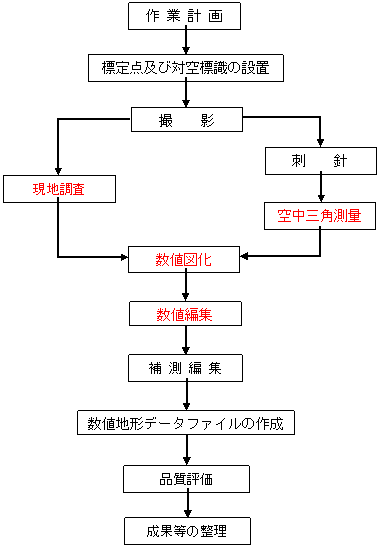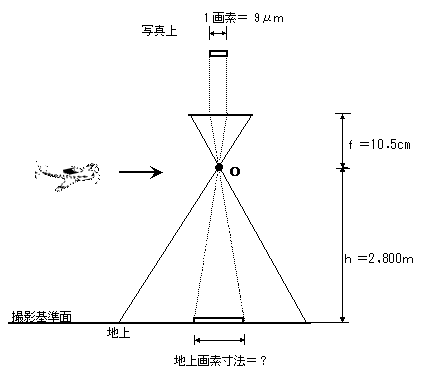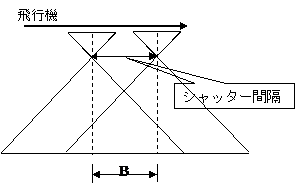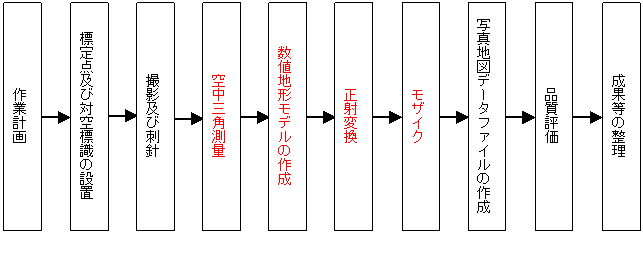| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
��No15�F�ʐ^���ʁF��
�@ �ʐ^�n�}�쐬�ɂ�����c�s�l�i���l�n�`���f���j�̓����Ɋւ�����ł���B�q�[�U���ʂł́A�c�d�l�i���l�W�����f���j�ƌĂ�A�݂��ɒ�`�͈قȂ邪���̊T�O�͑S�������ł���A�c�s�l���c�d�l�ƍl����悢�B�c�s�l�Ƃc�d�l�̂ǂ�����A�C�ӂ̒n����i�q�i���b�V���j��ɋ�悵�A���S�_�i�i�q�_�j�̒n�\�ʂ̕W���i���x�j���L�ڂ��ꂽ�f�[�^�ł���B
�ȉ��ɁA��蕶���̊e�I�����ɂ��ĉ������B
�F�@�S |
|
��No16�F�ʐ^���ʁF��
�@�ʐ^���ʂ̍�ƍH���Ɋւ�����ł���B�ʐ^���ʂƂ́A�ʐ^��p���Đ��l�n�`�}�f�[�^���쐬�����Ƃ������A�g20�N�̍�ƋK���i�����j�̉�����A�ʐ^���ʂ̍�ƍH���͏��̏o��ƂȂ����B
�@��蕶�̍�ƍH���ɓK���Ȍ��Ă͂߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�@����āA�K���Ȍ��̑g�����́A�Q�ƂȂ�B
�@�F�@�Q |
|
��No17�F�ʐ^���ʁF��
��f���@�Ǝʐ^�k�ڂɊւ�����ł���B�P�ʂɘf�킳�ꂸ�A���̂悤�ɍl���ĉ����悢�B �@�O�}���A���̂悤�Ɍv�Z����悢�B �@ �� 1�ʂ��́A0.000001���i1�~10�|�U�j�ł���B
����āA�ł��߂��I�����́A�R�@�ƂȂ�B
�F�@�R |
|
��No18�F�ʐ^���ʁF��
��s���x�ƎB�e������Ɋւ�����ł���B���̂悤�Ȏ菇�ʼn���悢�B
�@��s�@�̑Βn���x��b���ɒ��� 200�q/h ��55.556m/s
�A�B�e����������߂�B �@��蕶���A�I�[�o�[���b�v60���ł��邩��A�B�e�����B�́A�a �� �i1-���j�E���E�� ���A �i�a�F�B�e����� ���F�d���x�A���F�ʐ^��ʂ̑傫���A���F�ʐ^�k�ڕ���j �@B���i1�|0.6�j�~23�p�~8,000 ��736��
�B��s���x�ƎB�e���������V���b�^�[�Ԋu�����߂�B �@�n�ё��x 55.556m/s �̔�s�@�ŁA�B�e������� 736m�ł��邩��A 736����55.556��/�� =13.248�b��13�b
����āA�ł��߂��l�́A�Q�ƂȂ�B
�F�@�Q |
|
��No19�F�ʐ^���ʁF��
�@�ʐ^���ʂ̐}���Ɋւ�����ł���B�e�I�����ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�F�@�R |
|
��No20�F�ʐ^���ʁF��
�@�ʐ^�n�}�쐬�̍�ƍH���Ɋւ�����ł���B�ʐ^�n�}�Ƃ́A�ʐ^�𐳎˓��e�ɕϊ������摜�ł���AH20�N�x�����̍�ƋK���̏�������lj����ꂽ���ڂł���B
��蕶�̃A�`�G�ɓK���Ȍ����L���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
����āA���������̑g�����́A�S�@�ƂȂ�B �F�S |