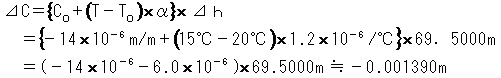| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
��No9�F�������ʁF��
�@���x���ɂ��ϑ���Ƃ̒��ӎ����Ɋւ�����ł���B��Ԗ��ł��邽�߂�������Ɨ������Ă����K�v������B�܂��A�I����3�Ɍ�����悤�ɁA�u�������ʂ̌덷�Ə����@�v�Ɋւ���I���������邱�Ƃ����邽�߁A�ϑ���Ƃ̒��ӎ����ƌ덷�Ə����@�̓Z�b�g�Ŋo����K�v������B�@�@ �ȉ��ɁA��蕶���̊e�I�����ɂ��ĉ������B
�@����āA���炩�ɊԈ���Ă���̂́A�T�ł���B �F�@�T |
|
��No10�F�������ʁF��
�@No9�Ɉ��������A���x���ɂ��ϑ���Ƃ̒��ӎ����Ɋւ�����ł���B�P���������ʂɌ����Ă̖��ł͂��邪�A���̂悤�ɐ����݂̂���������͏��߂Ă̏o��ƂȂ�B�ꌩ�A����悤�Ɏv���邪�A�ߋ�������Ȃ��Ă���Ηe�Ղɉł���B �ȉ��ɁA��蕶���̃A�`�I�ɂ��ĉ������B
�A�F�P�E�Q���������ʂł́A�ϑ����Ԓ������ނ�10�������Ɋϑ��Ɏg�p����@��̓_���������s���B �C�F�P���������ʂł̎��������͍ő�50���A�W�ږڐ��̓ǒ�l��0.1�o��W���Ƃ���B �E�F�P���������ʂł́A�W�ڂ̉���20�p�ȉ���ǒ肵�Ȃ��B �G�F�P���������ʂł́A�ϑ��̊J�n���A�I�����A�Œ�_���������ƂɁA�C����1�x�P�ʂő�������B �I�F�V�_�̊ϑ��́A�i�v�W���̐ݒu��24���Ԉȏ�o�߂��Ă���s���B�i��ƋK���̏��� ����Ɖ^�p�ł́A�u�ʏ�͂P�T�Ԓ��x���o�߂��Ă��炪�]�܂������A��ނ����Ȃ��ꍇ�ł�24���Ԉȏ�o�߂��Ă���s���v�Ƃ���j
�@����āA���������l�̑g�����́A�P�ƂȂ�B
�F�@�P |
|
<No11�F�������ʁF��>
�@��Ԗ��ƂȂ����A���x���̂����ł������@�i���x���̋C�A�ǎ��Ǝ������i���j�����s�i�����j�ł��邩�ǂ����̓_�����@�j�Ɋւ���v�Z���ł���B�Y�ł������@�̌����͂�◝�������������̂ł͂��邪�A���̏o��`���͗�N�����ł��邽�߁A��@�i�v�Z�̗���j��g�ɂ��Ă��܂��������ǂ��B�@�ȉ��ɁA�v�Z�̗���ɉ����ĉ���B
�@ �W�ڇT�E�U�Ԃ̐��������፷�����߂�B�i���x���ʒu�`�j 1.28989 �� �| 1.24579 �� �� 0.0441 ��
�A ���x���ʒu�a�Ŋϑ������A�W�ڇT�E�U�Ԃ̍��፷�����߂�B 1.14412 �� �| 1.09002 �� �� 0.0541 ��
�B �����̗L���肷��B �����Ń��x���̎������������Ȃ�A �@ �� �A�ł��邪�A�@�| �A �� 0.0441 �� �| 0.0541 �� �� �|0.0100 �� �ł��邽�߁A�������̒������K�v�ƂȂ�B �@�܂��A�����������m�ł���Ɖ��肷��Ȃ�A���x���ʒu�a����̊ϑ��ł́A�W�ڇU�̓ǒ�l�� 1.09002 �� �{ 0.010 �� �� 1.10002 �� �t�߂ł���ƌ�����B �� 1.10002 ���������l�ł͂Ȃ��B
�C �W�ڇU�̒����ʂ����߂�B �@���x���a�ɂ�����W�ڇU�̒����ʂ́A �@�]���ă��x���a����A�W�ڇU�̓ǒ�l�� 1.09002 �� �{ 0.011 �� �� 1.10102 ���@�ƂȂ�悤�ɁA������������悢�B
�@����āA�W�ڇU�̓ǒ�l�́A�S��1.10102 ���ƂȂ�B
�F�S |
|
<No12�F��> �@�W�ڕ�Ɋւ���v�Z���ł���B�W�ڕ�v�Z�����o���Ă����K�v�����邪�A�͂��̎��ɐ��l�������A�v�Z����悢�BH20�AH22�Əo�肳��Ă��邽�߁A����̏o��ɒ��ӂ��K�v�ł���B �@�ȉ��ɁA����B
�W�ڕ�͈ȉ��̎��ɂ��s����B�i�W�ڕ�v�Z�j
���b�F�W�ڕ�� �b�O�F����x�ɂ�����W�ڒ萔 �s�F�ϑ����̑��艷�x �s�O�F����x�i�W�ڒ萔�̊���x�j ���F�c���W�� �����F���፷
�� �W�ڒ萔�́A1����20���A2����15���̒l���K�p�����B �� �W�ڕ�ʂ́A���፷�̐�Βl�ɑ��ĉ������s���B �� �ϑ����̑��艷�x�́A1���������ʂł͊ϑ��̊J�n�A�I���A�y�ьŒ�_�ւ̓������ƂɁA�C����1���P�ʂő��肵���Ƃ��̕��ς��̗p����B
�O���ɖ��̐��l�Ă͂߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�� 14��m�i�}�C�N�����[�g���j�́A14�~10�|6m�ŁA14�^1,000,000 m�̎��ł���B
����āA���̍��፷�͎��̂悤�ɂȂ�B
�{�b69.5000m�|0.001390m�b�� �{69.49861m �� ���፷�̐�Βl�ɑ��Čv�Z���s���B
����āA�ł��߂��l�́A�u�P�v�� �{69.4986�� �ƂȂ�B
�F�P |