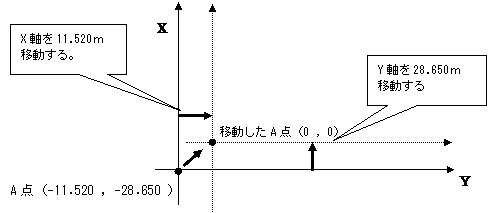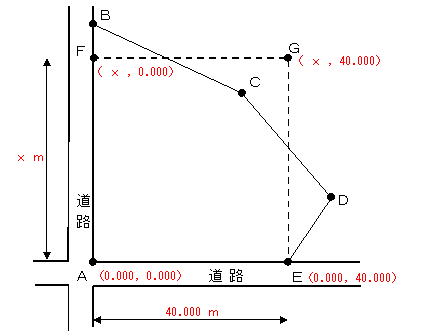| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<No25:応用測量:路線:解答>
以下に、各選択肢(路線測量の各工程)について解説する。
1.正しい。(線形決定) 2.正しい。(中心線測量) 3.正しい。(中心線測量) 4.間違い。(縦断測量) 5.正しい。(横断測量)
解答: 4
|
|
<No26:応用測量:用地:解答>
以下の手順で解答すれば良い。
1.座標原点を移動し、座標値を計算しやすい数値にする。
よって、境界杭 A,B,C,D,E で囲まれた土地の面積は、1768.000 ㎡ となる。
3.ここで問題の図を見ると、次のように考えられる。
求めるべき土地A,F,G,Eは、問題文より長方形であるため、その面積は、
40.000 m × x となる。
土地の面積を変えないため、2.で求めた面積を用いて、次の式を組み立てる。
1768.000 ㎡ = 40.000 m × x よって、x = 44.200 m
ここで、1.において、計算の都合上座標値を移動しているため、これを加えると次のようになる。
44.200 - 11.520 = 32.680
よって、点GのX座標は、32.680 mとなる。
解答:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<No27:応用測量:用地:解答>
以下に、a~eまでの各作業内容をその作業名に置き換えてみる。
a. 面積計算 b. 境界確認 c. 境界点間測量 d. 境界測量 e. 復元測量
これを用地測量の正しい作業工程に当てはめると次のようになる。
作業計画 → 資料調査 → 復元測量(e)→ 境界確認(b)→ 境界測量(d)→ 境界点間測量(c)
→ 面積計算(a)→用地実測図及び用地平面図データファイルの作成
よって、正しい作業順序で並んでいるのは、4となる。
解答: 4
|
|
<No28:応用測量:河川:解答>
次の手順で解答すればよい。
水系固有の基準面は、東京湾平均海面より1.300m低いため、 (東京湾平均海面)-(-1.300m) = (水系固有の基準面)となる。 解答:3
|