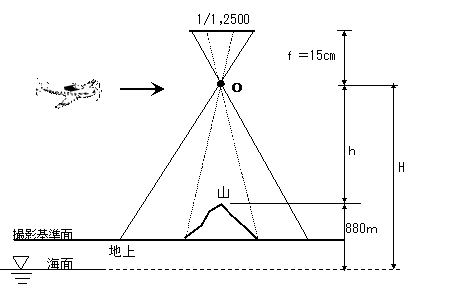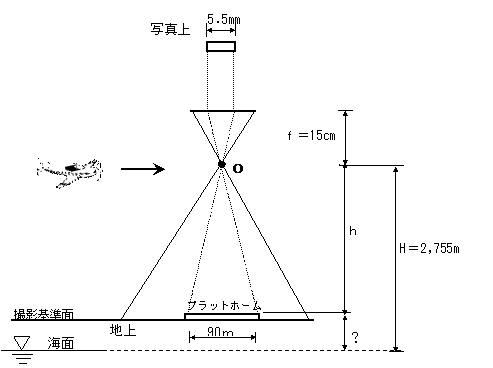| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<No15:写真測量:解答>
航空レーザ測量に関する問題である。H21年度に引続き出題された。航空レーザ測量の概要をしっかりと理解しておく必要がある。各選択肢について解説すると以下のようになる。
GPS装置は、GPS観測データを1秒以下の間隔で取得でき、2周波で搬送波位相を観測できる事。 IMU装置は、センサ部のローリング、ピッチング、ヘディングの3軸の傾き及び加速度が計測可能で、その取得間隔が0.005秒以上である事。 レーザ測距装置は、ファーストパルスとラストパルスの2パルス以上計測できる事、スキャン機能を有し、人体への悪影響を防止する機能を有する事。などが要求される。
よって、明らかに間違っている文書は、3となる。
解答: 3 |
|
<No16:写真測量:解答>
昨年度に引き続き、デジタルステレオ図化機に関する問題である。図化機に関する基礎的な問題であるため、過去問により図化機の特徴をつかんでおけば正しい選択肢を選ぶことができる。 問題文のア~エに適当な語句を記すと次のようになる。
a.
デジタルステレオ図化機は、コンピュータ上で動作するデジタル写真測量用ソフトウェア、コンピュータ、
ステレオ視装置 、ディスプレイ、三次元マウス又はXYハンドル及びZ盤などから構成される。
よって、正しい語句の組合せは、4である。
解答: 4 |
|
<No17:写真測量:解答>
近年、頻繁に出題される撮影基線長を求めさせる問題である。特に難しい計算ではないが、オーバーラップの算出式を覚えておく必要がある。また、海抜撮影高度≠撮影高度である事にも注意が必要である。以下に解説する。
この問題を解くためには、まず、撮影高度と画面距離の関係から写真縮尺を求め、これより写真に写る地上の範囲(距離)を求める必要がある。これより計算された値を用いて、撮影基線長を求めればよい。
撮影高度(H)= 4,000m - 400m = 3,600m
③
写真に写る、地上の範囲の計算
よって、撮影基線長Bは、2.2 km となる。
解答:3 |
|
<No18:写真測量:解答>
空中三角測量における、パスポイントとタイポイントの特徴に関する問題である。過去問をしっかりとこなしていれば、簡単に解ける問題である。選択肢は、H19とほぼ同じである。 以下に、問題文中の各選択肢について解説する。
1. 正しい。 パスポイントとは、同一コース内の隣接写真の連結に用いられる点を言う。言い換えると、2枚以上の空中写真を、コース方向に連結させるために設けられる点の事である。パスポイントは、重なり合う部分の、中央(主点付近)と両端に1点ずつ3点を選ぶ。
タイポイントとは、隣接コース間の接続に用いられる点で、隣接コースと重複している部分で、関係空中写真上で、明瞭に認められる位置に選定する。
パスポイントは、重なり合う部分の、中央(主点付近)と両端に1点ずつ3点を選ぶ。
ブロック調整では、コース間の歪みを調整できると言う事から、タイポイントをコースの重複部に「ジグザグ」に選択するのが良いとされている。
問題文の通りである。また、パスポイント及びタイポイントを選定しようとする場所の近辺に基準点があり、対空標識が明瞭に写っている場合は、基準点で代用する事もできる。
よって、明らかに間違っているのは、3である。
解答 3 |
|
<No19:写真測量:解答>
撮影高度と縮尺に関する問題である。撮影高度と海抜撮影高度の違いを理解し、海抜撮影高度を基準に計算すればよい。また、写真測量の計算問題全般に言える事であるが、必ず図を描き、問題を整理して解くようにすれば正答を導く事ができる。
1.山頂の撮影高度と海抜撮影高度を求める。
撮影高度は、 よって、海抜撮影高度は 1,875m + 880m = 2,755m
2.鉄道駅における縮尺と撮影高度を求める。 縮尺は、 撮影高度は、 1.で求めた海抜撮影高度を基に計算すると、 2,755m - 2,455m = 300m
よって、プラットホームが在る地点付近の標高は、3.の300m となる。
解答 3 |
|
<No20:写真測量:解答>
写真地図作成の作業工程に関する問題である。写真地図とは、空中写真を正射投影に変換した画像であり、H20年度改正の作業規程の準則から追加された項目である。 以下に解説する。
問題文のア~ウに適当な語句を記すと次のようになる。 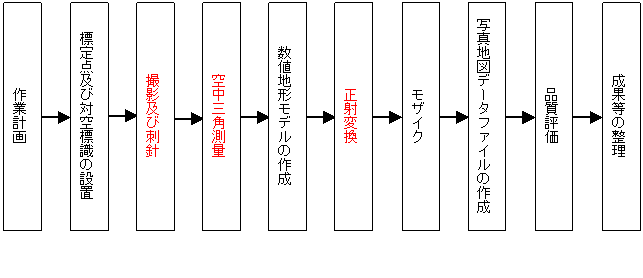 <写真地図作成の作業工程> 写真地図作成は、空中写真をスキャナにより数値化した数値写真や、デジタルカメラで撮影した数値写真をデジタルステレオ図化機等により正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業を言う。また、隣接する正射投影画像(デジタルオルソフォト画像)をモザイク処理し結合する、モザイク画像を作成する作業も含まれる。
<正射変換> 正射変換とは、本来中心投影で撮影されている空中写真を、正射投影機を用いて正射投影した像に変換する作業である。写真地図作成における正射変換とは、空中写真をスキャニングして数値化した数値写真又はデジタルカメラで撮影した数値写真を、デジタルステレオ図化機を用いて、内部標定や空中三角測量をPC上で半自動化し、モニタリングしながら正射投影写真画像(デジタルオルソフォト画像)を作成する作業を言う。
<モザイク> モザイクとは、隣接する正射投影画像の重複部分について、位置と色を合わせ接合する作業を言う。モザイクの手順は、次の通りである。 濃度補正 → 濃度変換による色あわせ → 接合点の探索 → 接合点周辺の濃度の平滑化
よって、正しい語句の組合せは、1 となる。 解答:1 |