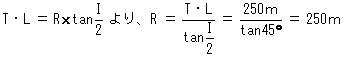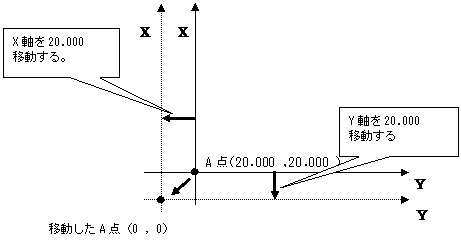| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
<No25:応用測量 路線:解答>
H6-7-A・H7-7-A・H8-7-B・H9-7-B・H14-7-A・H18-7-A・H21-25(出題回数 7/16) 単曲線設置に関する問題である。同様に単曲線の設置(IP杭が設置できない場合)と合わせると、14/16と言う、ほぼ毎年出題される定番問題である。単曲線の設置問題は、単曲線の公式や、各役杭(IPやBC、ECなど)の意味をしっかりと覚えておく必要がある。いわゆる図形の問題でもあるため、過去問題をしっかりとこなしパターンを理解しておくとよい。 今回の出題は、H18年度の類似問題である。過去問題を解いていれば確実に解ける問題であった。
次のように、考えて解けば良い。
(別解) 計画時のT・Lが250mであることを利用して考えると、次のようになる。 三角形 IP‐BC‐O′より、単曲線の性質から、∠IP - O′- BC = 45°、∠IP - BC - O′= 90°であるから、三角比により BC‐O′= 250m となる。
よって、単曲線の中心の移動量は、400m − 250m = 150m
解答 2 |
|
<No26:応用測量 路線:解答>
H17-7-B・H21-26(出題回数 2/16)
路線測量の作業工程に関する問題である。H17年度に続き2回目の出題となったが、難易度はさほど高くはなく、中心線測量→縦断測量・横断測量の流れが理解できていれば解くことができる問題であった。目を引くのは、「品質評価」と「メタデータの作成」の項目が追加されていることである、これは作業規程の準則に準じている。次年度以降は、この部分が問題として出題される可能性もある。
問題文のチャートに正しい語句を入れると次のようになる。
よって、適当な語句の組み合わせは、1となる。
解答: 1 |
|
<No27:応用測量 用地:解答>
7-7-C・H11-7-D・H12-7-C・H13-7-C・H15-7-D・H16-7-C・H18-7-C・H19-7-B・H20-7-B・H21-27 (出題回数 10/16) ● 解 答 定番となった、座標法による面積計算の問題である。決して難しい問題ではなく、計算表の作り方さえ覚えておけば解ける。また、問題に与えられた座標値を簡単な数値に直して計算するのも、解答手法である。
以下の手順で解答すれば良い。
1.座標原点を移動し、座標値を計算しやすい数値にする。
2.次のような計算表を作成し、数値を入れ倍面積、面積と計算する。
境界杭 A,B,C,Dで囲まれた土地の面積は、4 の 2,287.500㎡ となる。 解答:4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<No28:応用測量 河川:解答>
H14-7-B・H21-28 (出題回数 2/16)
河川測量における距離標設置測量に限った問題である。距離標設置測量は、河川測量における基礎とも言うべき測量であり、距離標を基にその後の定期縦横断測量が行われる。このため、距離標に関する問題は、河川測量に関する問題文中で選択肢の一つとして頻繁に出題される。距離標設置測量に限った出題はまれであるが、選択肢の一つとしては定番となっているため、その内容をしっかりと理解しておく必要がある。
問題文に適当な語句を当てはめると、次のようになる。
河川における距離標設置測量は, 河心線 の接線に対して直角方向の左岸及び右岸の堤防法肩又は法面などに距離標を設置する作業をいう。なお,ここで左岸とは 上流から下流 を見て左,右岸とは 上流から下流 を見て右の岸を指す。 距離標の設置は、あらかじめ地形図上に記入した 河心線 に沿って,河口又は幹川への合流点に設けた 起点 から上流に向かって200mごとを標準として設置位置を選定し、その座標値に基づいて,近傍の3級基準点などから放射法などにより行う。また,距離標の埋設は,コンクリート又は プラスチック の標杭を,測量計画機関名及び距離番号が記入できる長さを残して埋め込むことにより行う。
よって、正しい語句の組み合わせは、2となる。
解答: 2 |