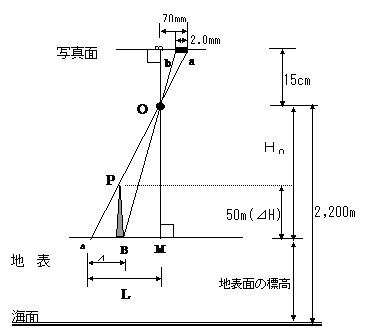| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
��No17�F�ʐ^���ʁF��
H6-5-B�EH9-5-B�EH14-5-B�EH17-5-B�EH19-5-B�EH21-17�i�o��@6�^16�j
�@�u�䍂�ɂ�鑜�̃Y���v�𗘗p���A���˂̍�����n�\�ʂ̕W�������߂�������ł���B2�`3�N�ɂP��̊����ŏo�肳�����ł��邪��H�����߂�������o���Ă����K�v������B�܂��A�̃|�C���g�́A��蕶����}��`����悤�ɂ��邱�Ƃł���B�ʐ^���ʂ̌v�Z���͂��̂قƂ�ǂ����v�Z�ɂ�苁�߂��邽�߁A�}���画�f�ł��邱�Ƃ������B
�㎮�ŋ��߂��̂́A�����̎B�e���x�ł��邽�߁A�n�\�ʂ̕W���͎��̂悤�ɋ��߂�B 2,200�� �| 1,750�� �� 450��
����āA�n�\�ʂ̕W����450���ƂȂ�B
�F�@�R |
|
��No18�F�ʐ^���ʁF��
H9-5-D�EH14-5-D�EH21-18�i�o��@3�^16�j
�v���Ԃ�ɏo�肳�ꂽ�A�u�X�L���i�[�̉𑜓x�v�Ɋւ�����ł���B�ȑO�́Adpi�i�h�b�g�p�[�C���`�j�ł̏o��ł��������A���N�x�͑f���Ɂu��f���v�ŏo�肳��Ă���B ���ʂ̒m���ƁA�f�W�^���@��̒m�����v���������ł����邪�A���e�I�ɓ�����̂ł͂Ȃ����߁A��������Ɨ������Ă����K�v������B
�@���̂悤�ɍl���ĉ����Ηǂ��B
�@ �n��̎B�e�͈͂̌v�Z �@��蕶���A�ʐ^�k��1/20,000�̋ʐ^�i23cm�~23cm�j�n��̎B�e�͈͂́A���̂悤�ɂȂ�B
�A �P��f�̎B�e��ʁi�n��j�ɂ�����͈͂̌v�Z �@23cm�~23cm�̋ʐ^���X�L���i�[�Ő��l�����A���̉�f����11,500�~11,500 �ƌ������́A �@23cm�^11,500 ���A�ʐ^��̂P��f�̃T�C�Y�ƂȂ�B
�@���̂��߇@�ŋ��߂��A�B�e�͈͂���f���Ŋ���A�P��f������̒n��i��ʏ�j�ł͈̔͂����߂��鎖�ɂȂ�B �@4,600���^11,500 �� 0.4�� �� 40�p �@����āA�B�e��ʏ�̂P��f�̃T�C�Y�́A40�p�~40�p�ƂȂ�B
�F�@�T |
|
��No19�F�ʐ^���ʁF��
H21-19�i�o��@1�^16�j
�@���N�x����o�肳�ꂽ�A�q�[�U���ʂɊւ�����ł���BH16�N�x�Ƀf�W�^���ʐ^���ʂɊւ���o�肪���������A��ƋK���̏����ɐV���ȍ��ڂƂ��ĉ���������ߏo�肳�ꂽ�ƍl����B �@��ƋK���̏����A281���`293��ӂ肩��o�肳��Ă���B����̏o����\�z����邽�߁A��蕶�����̂܂܊o���Ă��܂��̂��ǂ��B
�@��蕶�̃A�`�I�ɓK���Ȍ����L���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�q�[�U���ʂ́A�q��@�Ƀ��[�U�������u�A�@GPS/IMU�@ ���u�A�f�W�^���J�����Ȃǂ𓋍ڂ��āA�q��@����n��Ɍ����ă��[�U�p���X�˂��A�n�\�ʂ�n���Ŕ��˂��Ė߂��Ă������[�U�p���X����A�n�\�̕W���f�[�^�������x�������x�ɋ��߂邱�Ƃ��ł���Z�p�ł���B �擾���ꂽ���[�U�����f�[�^�́A�@�����p��_�@ �ł̌v���l�Ƃ̔�r��R�[�X�Ԃł̕W���l�̓_���ɂ��A���x���ƕW���l�������āA�@�I���W�i���@ �f�[�^�ƂȂ顂��� �@�I���W�i���@ �f�[�^�ɂ͍\������A���Ȃǂ��甽�˂����f�[�^���܂܂�Ă��邽�߁A�n�\�ʈȊO�̃f�[�^����菜���t�B���^�����O�������s���A�n�\�̕W������������ �@�O���E���h�@ �f�[�^���쐬����B �܂����[�U�����Ɠ������ɒn�\�ʂ��B�e�����摜�f�[�^�́A �@�I���W�i���@ �f�[�^����쐬���ꂽ���l�\�w���f����p���Đ��˕ϊ�����āA �@�����|���S���@ �f�[�^�Ȃǂ̎擾��t�B���^�����O�����̊m�F��Ƃɗ��p�����B �@�I���W�i���@ �f�[�^�͒n�\�̃����_���Ȉʒu�̕W���l�����z���Ă��邽�߁A���p�ړI�ɉ����Ēn�\���i�q��ɋ�����O���b�h�f�[�^�ɕϊ����邱�Ƃ�������O���b�h�f�[�^�́A �@�I���W�i���@ �f�[�^�̕W���l����A���}��Ԗ@��p���č쐬�����B
�@����āA���������̑g�����́A�u�P�v�ƂȂ�B
�F�@�P |
|
��No20�F�ʐ^���ʁF��
H7-5-D�EH10-5-A�EH12-5-D�EH13-5-D�EH15-5-D�EH16-5-D�EH17-5-C�EH19-5-D�EH21-20 �i�o��@9�^16�j
�@���l�}���@�̈�ł���A�f�W�^���X�e���I�}���@�̓����Ɍ��������ł���B�]���̏o����������I���������邪�A�ߋ���ɂ��f�W�^���X�e���I�}���@�̓���������ł����ΐ������I������I�Ԃ��Ƃ��ł���B �ȉ��ɁA��蕶���̊e�I�����ɂ��ĉ������B
�@����āA���炩�ɊԈ���Ă���I�����́A�Q�ł���B
�F�@�Q |