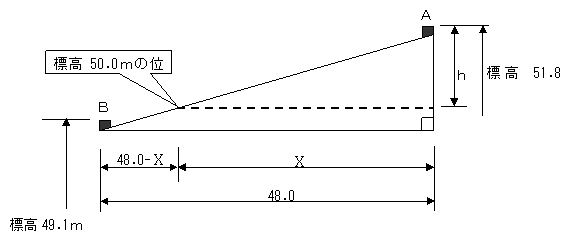| - PR - |
| - PR - |
| - PR - |
|
��No13�F�n�`���ʁF��
���@�֘A���iRTK-GPS���ʁj H20-4-B�EH21-13�i�o��@2�^16�j
�@��N�x�Ɉ������ARTK-GPS�@�ɂ��n�`���ʂɊւ�����ł���B �@��蕶�́A��ɍ�ƋK���̏���94������̏o��ł͂��邪�ARTK-GPS�@�Ɋւ���T�v���������Ă����K�v������B
RTK-GPS�Ƃ́A��_�i�Œ�_�j�Ɗϑ��_�i�ړ��_�j�œ����Ɋϑ����A��_�Ŋϑ������f�[�^���@���𗘗p���Ċϑ��_�ɑ��鎖�ɂ��A�f�o�r���ʋ@�̓����Ŋ����͂����A���^�C���i�P�b���Ɓj�ōs���A�ϑ��_�ō����x�̎O�������i�ʒu���j�������鑪�ʎ�@�ł���B RTK-GPS�@�̗��_�Ƃ��ẮA�ړ��_�̎O�������W�����A���^�C���ɘA�����Ċϑ��ł��邱�ƁADGPS�ɔ�ׁA�����x�i10�`30mm���x�j�����҂ł��邱�ƂȂǂ�����B ���Ɋւ��Ē��ӂ��ׂ��_�́A�]���o�肳��Ă���GPS�i�X�^�e�B�b�N�@�j�ϑ��@�Ɣ�r���A�q���̎g�p���ł���B�X�^�e�B�b�N�@�ł́A�g�p����q�������S�i10Km�ȏ�̊ϑ������ł͂T�j�ł��������ARTK�ł͂T�ȏ���g�p���邱�ƂɂȂ�B������g�p����q�����Ɋւ���o�肪�����܂�邽�߁A���ӂ��K�v�ł���B
�@�@��蕶�̃A�`�G�ɓK���Ȍ����L���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
RTK-GPS�@�ɂ��n�`���ʂƂ́A GPS���ʋ@��p���Ēn�`�}�ɕ\������n�`�A�n���̈ʒu�����n�ő��肵�A�擾�������l�f�[�^��ҏW���邱�Ƃɂ��n�`�}���쐬�����Ƃł���B RTK-GPS�@�ɂ��n�`���ʂł́A���d�͖����@�Ȃǂ𗘗p���Ċϑ��f�[�^�𑗎�M���邱�Ƃɂ��A �@�������@ �����A���^�C���ōs���邽�߁A���n�ɂ����Ēn�`�A�n���̑��Έʒu���Z�o���邱�Ƃ��ł���B RTK-GPS�@�ɂ��n�`���ʂɂ�����ϑ��́A �@���˖@�@ �ɂ��P�Z�b�g�s���A�ϑ��Ɏg�p����GPS�q���� �@�T �@ �ȏ�g�p����B ����RTK-GPS�@�ɂ��n�`���ʂ́A �@�ו������@ �̍H���ɗp���邱�Ƃ��ł���B
�@����āA���������̑g�����́A�u�P�v�ƂȂ�B
�F�@�P |
|
��No14�F�n�`���ʁF��
���@�֘A���i���n���ʁj H8-4-B�EH15-4-C�EH16-4-C�EH17-4-C�EH19-4-A�EH20-4-C �iTS��p�����ו����ʁj H21-14�i���n���ʁF�o��@1�^16�j
�@�n�`���ʂɂ����錻�n���ʂɊւ�����ł���B �@��ƋK���i�����j�̉���ɂ��A�n�`���ʂɊւ��鍀�ڂ͎��̂悤�ɕύX���ꂽ�B
�@�ȒP�Ɍ����A�����ʂ����n���ʂւƖ��́i���@�j��ύX���A�ו����ʂ����{TS�ɂ����@���ATS�{ RTK-GPS �ƂȂ����ƌ������ł���B �@����̏o��́A�������ꂽ��ƋK���̏���83���`85���Ɋւ�����ł���A�V�����o��ł���ƌ�����B��蕶����ƋK���̏������̂܂܂ł��邽�߁A���̂܂܊o���Ă��܂��̂��ǂ��B
�@�@��蕶�̃A�`�E�ɓK���Ȍ����L���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
a�D���n���ʂƂ́A���n�ɂ����ăg�[�^���X�e�[�V�����Ȃǖ���RTK�|GPS�@�Ⴕ���̓l�b�g���[�N�^RTK-GPS�@��p���āA���͕��p���Ēn�`�A�n���Ȃǂ𑪒肵�A �@���l�n�`�}�f�[�^�@ ���쐬�����Ƃ������B b�D���n���ʂ́A �@�S����_�@ �A�ȈՐ����_���͂���Ɠ����ȏ�̐��x��L�����_�Ɋ�Â��Ď��{����B c�D���n���ʂɂ��쐬���� �@���l�n�`�}�f�[�^�@ �̒n�}��x���́A�����Ƃ��� �@1000�@ �ȉ��Ƃ���B
�@����āA���������̑g�����́A�u�T�v�ƂȂ�B
�F�@�T |
|
��No15�F�n�`���ʁF��
���@�֘A���i�A�[�N�E�m�[�h�f�[�^�\���j H11-4-D�EH13-4-D�EH16-4-D�EH19-4-C�EH20-4-A�EH21-15�i�o��@6�^16�j
�@GIS�Ɏ�ɗp������x�N�^�f�[�^�̌`���i�A�[�N�E�m�[�h�f�[�^�\���j�Ɋւ�����ł���B �@���̃f�[�^�`�����A�_���A�����A�ʏ������ꂼ��A�m�[�h�A�`�F�[���A�|���S���̊W�ŕ\���Ă�����̂ł���A���ꂼ��̃f�[�^�ɂ́A�������ƌĂ��A�_�i���A�ʁj�ԍ���A���W�f�[�^�Ȃǂ��A�K�w�`���ɂ��t�����Ă���B
�@���̖��̉��@�Ƃ��ẮA�I�������Ƃɐ}����m�F���Ƃ�悢�����ł���B�ߋ�������������Ɨ������Ă���Ή�������ł���B�@�ȉ��ɁA�e�I�����ɂ��Ċm�F����B
�F�@�R |
|
��No16�F�n�`���ʁF��
���@�֘A���i����������j H13-4-B�EH18-4-A�EH20-4-D�EH21-16�i�o��@4�^16�j
�@�������Ɋւ����b�I�Ȍv�Z���ł���B��蕶��ǂ߂A���ɑ��ʂ̒m�����Ȃ��Ƃ��A���邱�Ƃ��ł���B �@�悸�A��蕶��}�ɕ`���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�@�����ŁA�_�`�`�a�����Ԑ���ŕW��50.0���̓������̈ʒu���l����ƁA�O�p�`�̑������A���̔�Ꭾ���g�ݗ��Ă���B �@2.7���@�F�@48.0���@���@1.8���@�F�@�]�@�@�@����������ƁA �] �� 32.0���@�ƂȂ�A�`�_����A �@32.0���̈ʒu�ɕW��50.0���̓�����������ƌ�����B
�@����āA1�^1,000 �n�`�}��ł́A�`�_����3.2cm�̈ʒu�ŁA�W��50.0���̓������Ƃ`�a�����Ԓ������H�̌�_������ƌ�����B
�F�T |