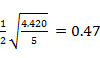| - PR - |
| - PR - |
|
<H27-No9:水準測量:解答>
公共測量における水準測量全般に関する問題である。問題各文について考えると次のようになる。
よって,間違っている文章は c,dとなる。
解答: 4 |
|
<H27-No10:水準測量:解答>
水準測量の「計算」に関する問題である。ア ~ オ に適当な語句を当てはめると次のようになる。
よって,正しい語句の組合せは 1 となる。
解答: 1 |
|
<H27-No11:水準測量:解答>
水準測量における観測方程式に関する問題である。
① ア,イ 問題文より, V1=X1-ア V2=-X1+X2+5.1004 V3=-X2-イ 新点Bの仮定標高は,30.0000m+5.2664m=35.2664m 新点Cの仮定標高は,-30.0000m-0.2108m=-30.2108m よって,ア=35.2664 ,イ=-30.2108 が入る。
② ウ 観測距離が,4.0㎞であり,路線(2)の重量を1としているため,1/4 = 0.25となる。 よって,ウ=0.25
③ エ V1-V2=0.25X1+X1-X2-(35.2664×0.25)-5.1004=1.25X1-13.9170 よって,エ=13.9170 が入る。
④ オ よって,オ=10.0050 が入る。
正しい数値の組合せは,2となる。
解答: 2 |
|
<H27-No12:水準測量:解答>
往復差から求める,1㎞当たりの観測の標準偏差を計算する問題である。 1㎞当たりの片道の標準偏差を求め,これを1/2すればよい。
よって,1㎞当たりの 往復の平均値の標準偏差は, 解答: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||