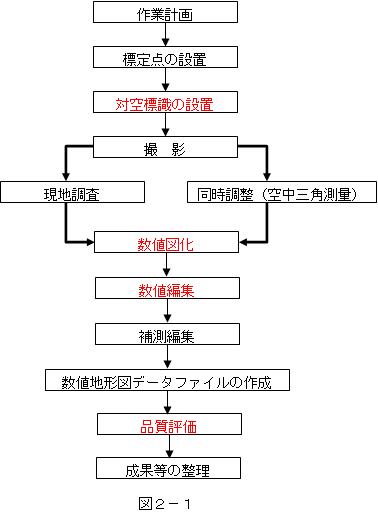| - PR - |
| - PR - |
|
�� H25-pm3-A�F�� ��
��A-1.
�����`�s�� �@�s�X�n�ȊO�́A���`�s�����������n�}��x��2500�̃f�[�^���g�p���A�s�X�n�̂ݐV�K���ƂƂ��Đ�������B
�����a���� �@�����̒n�}��x��2500�̃f�[�^�����y�n���@�̃f�[�^����ɏC������B
�����b���� �@���b���̒n�`�}���Q�l�����Ƃ��A���b���S���V�K���ƂƂ��Đ�������B
��A-2. �@�B�e���x���Ⴍ�Ȃ�̂ŁA�p���X���[�g���グ���X�L�����p�x����������B
��A-3. �ŋߗז@ �F�@�i�q�i�O���b�h�j�_�ɍł��߂��W���_�f�[�^���g�p����B �s�h�m �F�O���E���h�f�[�^�̓_������ŕs���O�p�Ԃ������A���̖ʂ̍�������}����B �o�C���j�A�@ �F�i�q�_���͂�4�_(�`16�_)�̕��ρB �N���M���O�@ �F�C�ӂ̕W���_�f�[�^�̕��ρB |
|
�� H25-pm3-B�F�� ��
��B-1. ��B-2. �@�B�e�H���ɂ����鐔�l�ʐ^�̓_�����ڂɂ��ċL�����B
����ƋK���̏��� ��145��2�@�i���������������l�ʐ^�̓_���j�� �E �B�e���x�E�B�e�R�[�X�̗ǔ� �E ���̋��̗L�� �E �w�W�y�ьi�C�̖��ēx �E �X���y�щ�]�ʂ̓K�� �E �ʐ^�����A���l�ʐ^�̓��������̗ǔ� �E ���l�ʐ^�̉掿 �ȂǁB
��B-3. �@���n�����Ŏ��{������e�ɂ��ċL�����B
����ƋK���̏��� ��168���@�i���n�����̎��{�j�� �E �\�@���ʂ̊m�F �E ���Ǎ���邢�͕s�\�Ȏ����̊m�F �E �B�e��̕ω��� �E �}���̓K�p�ɕK�v�Ȏ��� �ȂǁB
��B-4. �@�⑪�ҏW�ɂ����Ċm�F�y�ѕ�����鎖���ɂ��ċL�����B
����ƋK���̏��� ��192��1�@�i�⑪�ҏW�̕��@�j�� �E ���E�y�ђ��L �E �ҏW����Ȏ��� �E �B�e��̕ω��� �E �e��Ώە��̕\���̌��E�E�� �E ���n�����ȍ~�ɐ������ω��Ɋւ��鎖�� �E �ҏW��Ƃɂ����Đ������^�⎖���y�яd�v�ȕ\������ �ȂǁB |
|
�� H25-pm3-C�F�� ��
��C-1. �@�n���f���@�͎��̂悤�ɋ��߂�悢�B �@�I�[�o�[���b�v60���ł��邽�߁A�ʐ^��̊�����i��_������Fb�j�́A �@B��9,420�i�B�e����ƕ��s�ȒZ�Ӂj�~7.2�ʂ��i0.0000072���j�~�i1-0.6�j�� 27.13�o �@�����ŁAf/H �� b/B ���AB/H �� 27.13�o / 100�o�� 0.2713�@�ƂȂ�B �@��蕶�̒n���f���@�̎��ɓ��Ă͂߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �@300�o �~ 2 �~ 0.2713�@�@�`�@�@375�o �~ 2 �~ 0.2713�@�� 162.78�o�@�@�`�@�@203.48�o �@��蕶���A�n���f���@�͍ŏ��̒l�ł��邽�� �@162.78�o�@���@16�p�@�ƂȂ�B
��C-2. �@�C���B�e���x�͎��̂悤�ɋ��߂�悢�B �@�ʐ^�k�ځ��i��f���@�^�n���f���@�j�~ �@���@0.0000072�� / 16�p�@�� 1 / 22,222 �@�Βn�B�e���x�́A22,222�~10�p �� 2,222�� �@����āA�C���B�e���x�́A�@2,222���{100�� �� 2,322���@�@�ƂȂ�B
��C-3. �@�ŏ��B�e�R�[�X���͎��̂悤�ɋ��߂�悢�B �@��ʂ̎B�e�͈́i��k�j�́A14,430��f �~ 16�p �� 2,308.8���@ �@�R�[�X�Ԋu�́A�T�C�h���b�v��30���ł��邽�߁A�@2,308.8�~�i1�|0.3�j�� 1,616.2�� �@�R�[�X���́A12�q / 1,616.2�� �� 7.42 �R�[�X�@ �@����āA8�R�[�X�K�v�ƂȂ�B
��C-4. �@�B�e�ʐ^�����͎��̂悤�ɋ��߂�悢�B �@��ʂ̎B�e�͈́i�����j�́A9,420��f �~ 16�p �� 1,507.2�� �@�P�R�[�X������̖����́A�I�[�o�[���b�v��60���ł��邽�߁A 1,507.2 �~�i1�|0.6�j�� 602.9���@�@����āA19�q�@/ 602.9���@���@31.5 �� �@��蕶���A�R�[�X���[�̎B�e���O�ɂP���f�����B�e���邽�߁A 31.5���{3�� �� 35��/�R�[�X�@�@�@�@����āA8�R�[�X �~ 35�� ��280���@�ƂȂ�B |
|
�� H25-pm3-D�F�� ��
��D-1. �@���������Ă͂߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�B
GNSS/IMU���u�Ƃ́A�ʐ^�̘I�o�ʒu�y�јI�o���̌X���̎Z�o��ړI�Ƃ��āAGNSS���ʋ@�y��IMU���u�i�����v�����u�j�A��̓\�t�g�E�F�A���ō\�������V�X�e���ł���B GNSS/IMU���u��p�����B�e�ł́A�B�e�O��� �@�����l�o�C�A�X�@ ����y��IMU�h���t�g�������̂��߂̔�s���s���B�܂��AGNSS/IMU���u�̃f�[�^�́A�B�e�̑O��ɘA������ �@5�@ ���ȏ�擾����B �Œ�ǂ͎B�e�Ώےn����Ƃ̊������������ �@50�@ �L�����[�g���ȓ��Ƃ��顂܂��A�Œ�ǂɂ� �@�d�q��_�@ ��p���邱�Ƃ��ł���B GNSS/IMU���u�̉�͏����ɂ��O���W��v�f�́A�Œ�Njy��GNSS���ʋ@�̊ϑ��f�[�^��p���� �@�L�l�}�e�B�b�N��́@ ���s���A���̌��ʋy��IMU���u�̊ϑ��f�[�^��p���� �@�œK�O�Չ�́@ ���s�����ƂŎZ�o����B ����ɁA�e�ʐ^�̊O���W��v�f�����肷�邽�߂ɂ́AGNSS/IMU���u�̉�͏������Z�o���ꂽ�O���W��v�f�ƃf�W�^���X�e���I�}���@��葪�肳�ꂽ�p�X�|�C���g�y�у^�C�|�C���g���тɊ�_���̎ʐ^���W�Ƃ����Ē����v�Z���s���B
��D-2�D �@GNSS/IMU���u�̉�͌��ʂ̓_�����ڂ��L�����B
�@����ƋK���̏��� �� 134��2�3�4�@�iGNSS/IMU ��͌��ʂ̓_���j�� �E �Œ�Njy�эq��@���ڂ̂f�m�r�r���ʋ@�̍쓮�y�уf�[�^���^�̗ǔ� �E �T�C�N���X���b�v�̗L�� �E �f�m�r�r�^�h�l�t�B�e�͈͂̊m�� �E �v�����x�y�ьv���R�[�X�̗ǔ� �E �B�e�R�[�X��ɂ�����ŏ��q���� �E �B�e�R�[�X��ɂ�����c�n�o�i�o�c�n�o�A�g�c�n�o�A�u�c�n�o�j�l �E �݉c�R�[�X��ɂ�����ʒu�̉������̍� �E �ʒu�̕W�����̕��ϒl�ƍő�l
��D-3. �@�^�C�|�C���g�A�p�X�|�C���g�̔z�u�ɂ��ė��ӂ��鎖�����L�����B
����ƋK���̏��� ��160��1�2�@�i�p�X�|�C���g�y�у^�C�|�C���g�̑I��j�� �i�p�X�|�C���g�j �E ��_�t�ߋy�ю�_����ɒ��p�ȗ������̂R�ӏ��ȏ�ɔz�u���邱�Ƃ�W���Ƃ���B �E ��_����ɒ��p�ȕ����́A�㉺�[�t�߂̓������ɔz�u���邱�Ƃ�W���Ƃ���B
�i�^�C�|�C���g�j �E �אڃR�[�X�Əd�����Ă��镔���ŁA�ʐ^��Ŗ��ĂɔF�߂���ʒu�ɁA������ɂȂ�Ȃ��悤�W�O�U�O�ɔz�u���邱�Ƃ�W���Ƃ���B �E �z�u����_���́A�P���f���ɂP�_��W���Ƃ���B �E �p�X�|�C���g�Ō��˂Ĕz�u���邱�Ƃ��ł���B
��D-4. �@�u���b�N�����v�Z�ɂ����ė��ӂ��鎖�����L�����B
����ƋK���̏��� ��159��2�@�i�W��_�̑I��j�� �E �H���B�e�ɂ����ẮA�e�R�[�X�̗��[�̃��f���ɏ㉺�e�P�_�z�u����B �E ���B�e�ɂ����ẮA�u���b�N�̎l���t�߂ƒ������t�߂Ɍv�T�_�z�u����B �E ���B�e���������ɂ܂�����ꍇ�́A�e�B�e���̃R�[�X���ɕW��_���̂������Ȃ��Ƃ��P�_�̕W��_��z�u����B
|