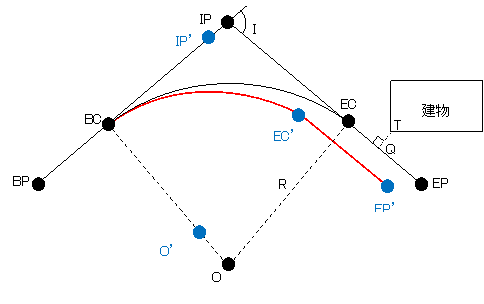| - PR - |
| - PR - |
|
<H23-pm5-A:解答例>
問A-1.
問A-2.
問A-3. 標杭設置の具体的作業内容を挙げる問題である。(作業規程の準則 第355条) ・4級以上の基準点から放射法により主要点には役杭を、中心点には中心杭を設置する。 ・役杭には、引照点杭または保護杭を設置する。 |
|
<H23-pm5-B:解答>
問B-1. ア:細分 イ:登記記録 ウ:復元測量 エ:境界確認 オ:公図等転写図 カ:4級 キ:境界点間測量 ク:用地境界仮杭設置 ケ:座標法 コ:250
問B-2. ア:100 イ:1 (作業規程の準則 第405条3) |
|
<H23-pm5-C:解答例>
問C-1. 問題文中の図に設置すべき中心杭、用地幅杭及び用地境界仮杭の本数を求める。 中心杭6本、幅杭14本、仮杭10本 ※必ず、問題文の図に書込んで確認する必要がある。
問C-2. TSを用いて用地境界仮杭を設置する方法を記す問題である。 「用地幅杭線と境界線の交点を視通法により行う。」 (作業規程の準則 第407条) |
|
<H23-pm5-D:解答例>
問D-1. 問題文中の表を完成させる問題である。 表中の数値から全て求められるので、決して難しい問題ではない。
ア:287.677 イ:0.003 ウ:0.575 エ:0.061 オ:372.947
問D-2. 距離標 河心線に沿って200メートル間隔を基準とし、3級基準点等から放射法により設置する。 (作業規程の準則 第375条)
水準基標 水位標に近接した位置に、5キロメートルから20キロメートル間隔を標準とし、2級水準測量により設置する。 (作業規程の準則 第377条)
問D-3. 深浅測量において、船位を測定するために使用する測量機器を答える問題。
船位の測定のため、「TS(トータルステーション)」と、「GNSS(GPS)測量機」のみである。 (作業規程の準則 第383条2)
|