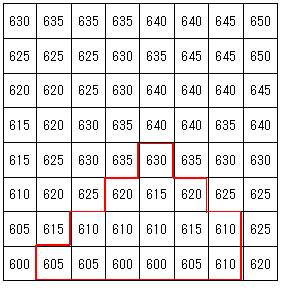| - PR - |
| - PR - |
|
<H22-pm3-A:解答例>
問A-1.デジタル航空カメラの利点を解答する。
・直接デジタルデータとして取り込むため、数値化する必要が無い。 ・写真処理が早く、画像化するまでの時間が短い。 ・画像劣化が殆どない。※カラーの写真地図作成において。
問A-2.撮影終了後における再撮影の要否を判定する点検項目を答える。
作業規程の準則第138条2によれば、次のような点検項目がある。
・撮影高度の適否 ・撮影コースの適否 ・実体空白部の有無 ・指標及び計器の明瞭度 ・写真の傾き及び回転量の適否 ・写真処理の良否 ・数値写真の統合処理の良否 ・数値写真の画質 ・雲及び光量不足等により数値写真が著しく不明瞭な時
問A-3.正射変換及びモザイクの留意事項と講ずるべき処置を答える。
1.正射変換 留意事項:構造物のひずみ 講ずるべき処置:ひずみの個所で、ブレークラインを取得し、正射変換を行う。
2.モザイク 留意事項:色調の差(濃度変化の平滑化) 講ずるべき処置:色調変化の少ない個所を接合部とすることにより、色調の差を目立たせない。 撮影時期や作業者が異なる数値写真を接合する場合、接合部の濃度変化を目立たせない。 |
|
<H22-pm3-B:解答>
問B-1.撮影高度を求める問題
地上画素寸法20㎝のものが、画像面での画素寸法12ミクロン(μm)になるため、その写真縮尺は、0.000012/0.2 = 1/16666.7 となる。 また、基準面の対地高度は、画面距離をかけて、0.12m×16666.7=2000m となる。 よって、撮影高度は、2000m+100m(標高)= 2100m となる。
解答:2100m
問B-2.撮影最小コース数を求める問題
問題文より、画像サイズは、縦(0.16589m)×横(0.09216m)であるため、コース間隔は、 (0.16589m×16666.7)×(1-0.3)=1935.387m≒1935㎞ となる。 問題文より、南北両端の撮影コースでは撮影区域外を画面の大きさの20%以上含むようにする。とあるため、0.16589m×16666.7×0.2=552.968m≒0.553㎞ よって、撮影コース数は、(11㎞+0.553㎞)÷1.935㎞ = 5.971 となり、6コースとなる。
解答:6コース
問B-3.最小写真枚数を求める問題
問題文から、撮影基線長を求めると、(0.09216m×16666.7)×(1-0.6)=0.614㎞ となる。 よって、必要モデル数は、14㎞÷0.614㎞=22.8≒23モデルとなる。 実体モデル23には、写真24枚が必要であるため、これに前後2枚を加えて、1コース26枚となる。 よって、26枚×6コース=156枚 必要となる。
解答:156枚 |
|
<H22-pm3-C:解答>
地上座標系とカメラ座標系の変換式を求める問題。また、ア~エは回転変換の公式、オ~クは共線条件式である。対策としては、暗記しておくしかないであろう。
<φ回転> ア:cosφ イ:sinφ
<κ回転> ウ:cosκ エ:sinκ
<共線条件式> オ:Xp―Xo カ:Yp―Yo キ:Zp―Zo ク:直線 |
|
<H22-pm3-D:解答>
問D-1.航空レーザ測量によりDEMを作成する場合の作業工程を答える。 ア~オに入る最も適当な語句は次の通りである。
ア:三次元計測データ作成
問D-2.土砂が流出した範囲を図示し、流出土砂の数量を求める問題 <流出土量>
メッシュの総数15個、平均変化高 {(5×4)+(10×10)+(15×1)}/15 = 9m
メッシュの面積は、10×10=100㎡ よって、流出土量は、100×15×9 =13500m3 となる。
解答:13500m3 |