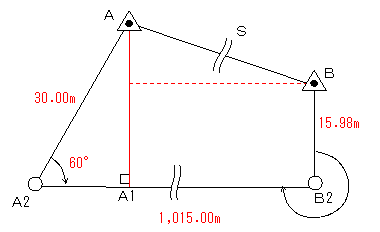| - PR - |
| - PR - |
|
<H22-No5:基準点測量:解答>
誤差論に関する問題である。この程度の事は理解しておきたい。 以下に、ア〜オ に入る適当な語句を以下に示す。
ア. 「真値」 イ. 「最確値」 ウ. 「系統」 定誤差ともいうが、意味的に問題があるので文中の表記が一般的。 エ. 「偶然」 不定誤差ともいうが、誤差論的には偶然誤差というべき。 オ. 「過失」 通常、不注意(ミステーク)は誤差とは呼ばない。問題文は経験不足な場合の例である。
解答: 3
|
|
<H22-No6:基準点測量:解答>
公共測量における1級基準点測量に関する問題である。選択肢1に見られるが、例年、試験問題は当年度の法規改正をただちに取り入れないものなのに、昨年度はわざわざ試験年一月現在で有効な法規や条約・規程などと試験案内に明記していた。本年はこのコメントがなかったが、おそらく「以後は前年に同じ」ということなのだろう。
以下、各選択肢について解説する。
解答: 5
|
|
<H22-No7:基準点測量:解答> 次の手順のように考え、計算すればよい。 (1) A〜S1へ垂線を下ろした点をA1とする。 (2) A〜A1の距離は、25.98m(30.00×sin60°)なので、B〜B2の距離15.98mを引けば残り10.00m。 (3) A2〜A1の距離は、15.00m(30.00×cos60°) (4) A1からB2の距離は1000.00m(1015.00m−15.00m)。 (5) よって、ピタゴラスの定理でSは1000.050mとなる。
解答: 1
|
|
<H22-No8:基準点測量:問題>
GPS測量機を用いた観測に関する問題である。 以下に、各選択肢について解説する。
解答: 2
|