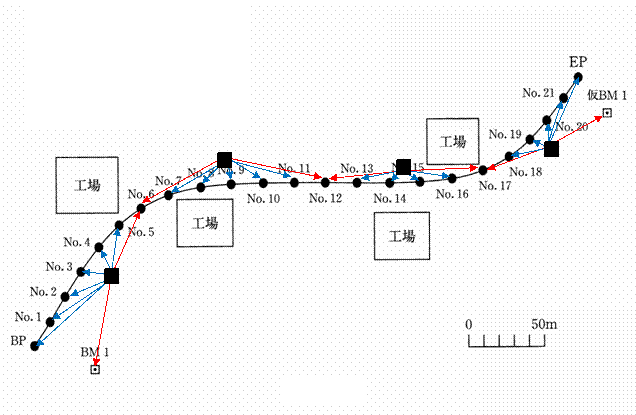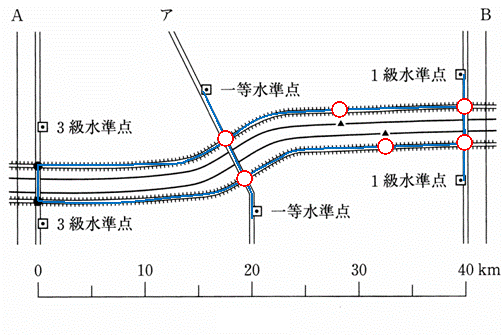| - PR - |
| - PR - |
|
<H21-pm5-A:解答例>
問A-1 器高式の水準測量が理解できていれば解ける問題である。ただし、注意点として次のような事項がある。 ・後視と前視を、一直線、また等距離になるように配置すること。 ・器械のセット回数を偶数回にすること。 ・縦断測量は4級水準測量に準じることになっているため、最大視準距離80mに従うこと。
解答例を図示すると、次のようになる。
問A-2 ・中間視では視準距離が不倒距離となるため、レベルの視準軸の点検調整を十分に行う。 ・工業地帯であると推察できるため、交通による振動には十分に注意を払い、地盤堅固な場所に据付ける。 ・軟弱地盤に据付ける必要がある場合は、脚杭等を設置する。 ・標尺の底面摩耗や表面(目盛面)のキズなどを事前に確認する。
※基本的に、水準測量に関する注意事項が記載されていればよいと考える。 |
|
<H21-pm5-B:解答>
用地測量の作業工程及び内容について問う問題である。以下に当てはまる語句を記す。
ア.作業計画 イ. 土地登記簿(土地登記記録) ウ.境界杭
|
|
<H21-pm5-C:解答例>
問C-1 ・関係権利者の権原及び意見の尊重 ・関係権利者の個人情報等に関する守秘義務の順守 ・関係権利者であることの確認 など。
問C-2 758.61 ㎡
点Bの座標値 X: 11,055.50 + 10 cos210° = 11,046.84 Y: 14,090.00 + 10 sin210° = 14,085.00
面積計算
|
|
<H21-pm5-D:解答例> <注意点> ・水準基標は2級水準測量なので3級水準点を与点とすることはできない。 ・A~アの間には、地盤沈下が観測されているため、水準基標を設置できない。 ・水位標に隣接するように水準基標を設置する。
問D-2 基本的に、上記注意点にあるような事を列記すればよい。その他としては、次のようなことが考えられる。 ・測量区域に等密度になるようにすること。 ・利用しやすく、後続作業においても発見が容易な場所であること。 ・地盤が堅固で、交通の支障が無く、保存に適した場所であること。 ・設置間隔が 5㎞ ~ 20㎞ であること。 その他。 問D-3
|