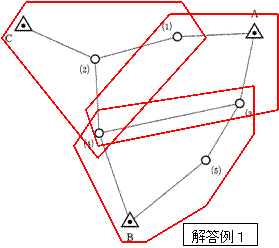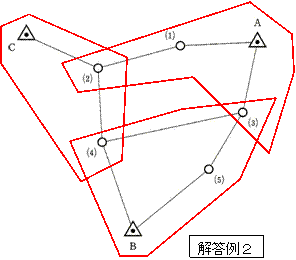| - PR - |
| - PR - |
|
<H21-pm2-A:解答>
基準点測量の作業工程に関する問題である。選択肢があるため、比較的楽に解ける問題である。作業工程に関しては、しっかりと覚えておきたい。問題文中の表に解答を当てはめると次のようになる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<H21-pm2-B:解答例>
GPSを用いた基準点測量に関する問題である。B-1には、定番とも言える観測図の作成がある。特に観測図の作成については、基本事項をしっかりと理解しておく必要がある。
問B-1. 観測図の作成例を挙げると次のようになる。 ポイントは、隣り合うセッションの新点を重複させる、新点数を等しくする、新点の無駄な重複を極力抑える事である。 |
|
<H21-pm2-C:解答例>
電子基準点の身を既知点とする、基準点測量に関する特徴を答える問題である。 以下に、各設問に関して解答例を記す。
問C-1.作業上の利点を4つ(それぞれ30字以内) (例) 与点成果に変動や経年変化の恐れがない。 (19字) 新点が常に与点内部にあって囲まれている。 (20字) 測量網設定配置の自由度が高いこと。 (17字) 既知点間の路線長の制限がないこと。 (17字) 既知点の点数を少なくできる。(14字) 単路線方式で計画できる。(12字) その他
問C-2.作業上の注意点を2つ(それぞれ40字以内) (例) 基線長によっては二周波受信機が必要。(18字) 問C-3.点検計算の方法(40字以内) |
|
<H21-pm2-D:解答例>
結合多角方式による基準点測量において、多角網形成について考慮しなければならない項目を記す問題。以下に、項目例を列記する。
路線長と辺数 既知点数 新点の配点密度 新点間における距離 交点に接する路線数 その他 |