| H20年度 測量士試験 午後No3 選択問題 解答例 |
|
< H20pm-No3-A:解答例 >
問 A-1
空中写真撮影に関する計算問題である。コース本数と写真枚数、空中写真測量に関する基本的な公式を理解していれば解ける問題である。
問題文中の「コース両端に1モデル分余分に…」と「南北両端のコースでは、作成範囲外を画面の大きさの15%以上…」の文書に注意する。
・海抜撮影高度の計算
表3-1から、H =(12,500 × 0.15)+100m = 1,975m
・コース本数の計算
表3-1から、コース間隔 = 0.23×(1-0.3)×12,500 = 2.012km
コース本数は、10km ÷ 2.021km = 4.95 ≒ 5本
※ 表3-1より、作成範囲外を画面の大きさの15%以上を含む必要があるため点検。
撮影範囲(南北方向)10km+{(0.23×0.15)×12,500 ×2}m = 10.863km 必要である。
2.021km × 4(間隔) = 10.06km コース両端から撮影される範囲は、
0.23m × 12,500 = 2.875km よって、10.06+2.875 = 12.935km > 10.863km 「OK」
・1コースの写真枚数の計算
表3-1より、コース両端には作成範囲外に各1モデル分余分に撮影する必要があるため、
{14km+(1.150km×2)}÷ 1.150km = 14.17 ≒ 15
つまり、基線長が15間隔必要となるため、写真の枚数は、15間隔 + 1枚 = 16枚 となる。
よって、写真枚数は、コース本数5本であるため、16枚×5本 = 80枚
解答:海抜撮影高度 = 1,975m コース本数 = 5本 写真枚数 = 80枚
問 A-2
基準点配置の注意事項を答える問題である。以下に、解答例を記す。(それぞれ40字以内)
・ 最低でもブロック四隅と中央に基準点を配置し、2コースごとに標高点を追加する。(38字)
・ 基準点をコース両端では6モデルごとに1点、以後30モデルごとに1点追加する。(38字)
ポイントは、水平位置の基準点の配置(四隅、中央)と標高の基準点の配置(2コースごと)である。
|
|
< H20pm-No3-B:解答例 >
問 B-1
TSを用いた細部測量に関する問題である。以下のポイントに留意して文章を組立てればよい。
・ 後方交会法によりTS点(補助点)の設置
※ 問題文中に基準点にTSの設置が困難とあるため、作業規程の準則(以下 準則)(第91条の2)にあるような、放射法による設置はできないと考える。
問 B-2
RTK-GPS測量に関する問題である。次のような点に注意して文章を考えればよい。
1. 地域が3点以上の(電子)基準点に囲まれた範囲にあり仮想点を生成できるように選定。(40字) (準則 第96条 3 - 一・二)
2. アフィン変換・ヘルマート変換・コンフォーマル変換・重み付き補間 など
3. 基準点などの座標既知の点との相互関係や地物同士の幾何学的条件などで点検する。(38字)
(当該地形データと隣接する1点以上の地形データで、座標補正前と座標補正後の距離の点検を行う。:準則 第96条3- 四 -ニ) |
|
< H20pm-No3-C:解答例 >
問 C-1
数値地図データに関する問題であるが、後述のデータ品質要求を熟読すれば十分解答することができる。以下に解答例を記す。
水域界
水域界起終点の交差及び不一致。(15字)
鉄道中心線
連続部分の不要な分断。(11字)
道路中心線
交差点以降の取付け道路の遺漏。(15字)
問 C-2
数値地図データの利用に関する問題である。以下に解答例を記す。
・道路路線図等の作成のおりに立体交差と誤認する。(23字)
|
|
問 D-1
正射投影と中心投影の違いについて問う問題である。以下の点に注意して文章を組立てればよい。
・ 空中写真 → 中心投影:航空カメラのレンズ中心を投影中心として点対称に投影面に投影される。写真主点を中心に高層物ほど放射状に傾いて投影される。
・ 正射写真 → 正射投影:対象物が投影面に対して鉛直に投影される。真上から見たように投影される。
問 D-2
中心投影で投影された地物がどのような形状で投影されているかを問う問題である。
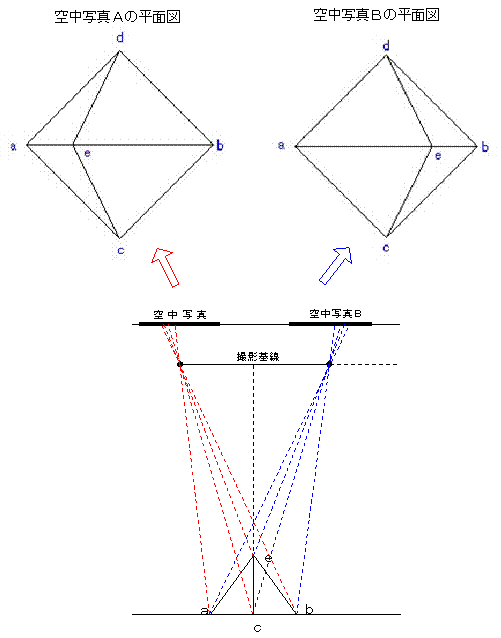
問 D-3
正射投影による投影面への投影図を描く問題である。
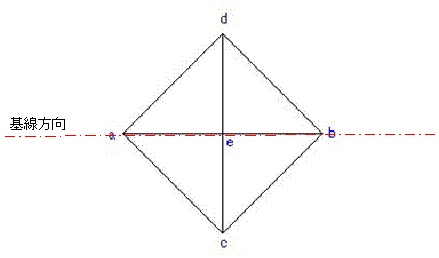
|
|
| 参考文献:公共測量作業規程 |
|
|