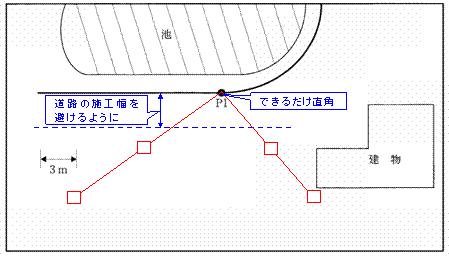| - PR - |
| - PR - |
|
< H19pm-No5-A:解答例 > (設置場所) ・地盤堅固で見通しが良い。 ・施工に際して破損の恐れが無い。 ・見通しが確保される。 (設置) ・役杭に交わる2線が「直角」になる。 ・対面の引照点同士を結ぶ線が平行(近く)になる。 |
|
< H19pm-No5-B:解答例 > |
< H19pm-No5-C-1:解答例 >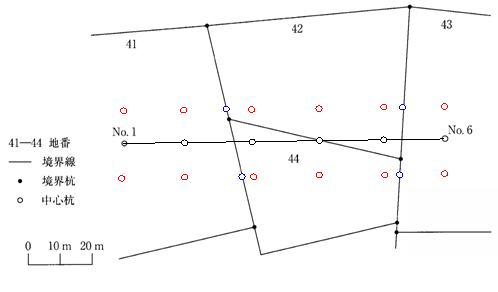 |
| < H19pm-No5-C-2:解答例 > 用地境界仮杭を設置するための測量方法については、次のような事柄について記せばよい。 ・TSによる放射法:境界測量と計算に基づき設置 ・TSによる交会法:平板測量で得た境界線の交点を現地に設置 |
| < H19pm-No5-D-1:解答例 > 距離標の杭高標高が13.20mであり、横断測量による比高が一番低いのが測点9の-6.20mであるため、これを用いて計算すると次のようになる。 13.20m - 6.20m = 7.00m |
表5-1を基に、グラフを書く要領で描けばよい。なお、間即時の水面は、WL(Water Line)の位置である。
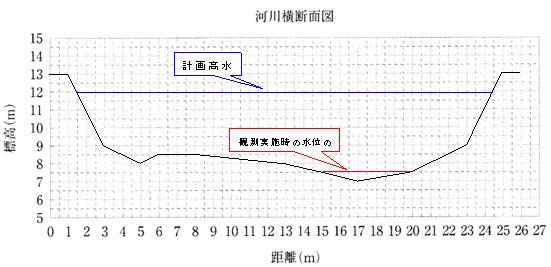 |
| < H19pm-No5-D-3:解答例 > 河床部の平均河床高は、次のように求めればよい。 9.00m - 20.00㎡ / 20.00m = 8.00m 表法尻からの断面積(20.00㎡)を左岸表法尻(測点3)から右岸表法尻(測点11)までの水平距離(潤辺※)で割ると深さ1.00m。これを表法尻の標高に加える。 ※ 潤辺(じゅんへん)長:ここでは、左岸表法尻から右岸表法尻までの水平距離を指す。一般には、水等の液体とそれを流すための面が接する部分の長さを言う。 |
| < H19pm-No5-D-2:解答例 > 計画水位高における流水部の断面積は、次のように求めればよい。 20.00㎡ + 64.50㎡ = 84.50㎡ (前出の表法尻からの断面積に表法尻から計画高までの面積を加算する。) |