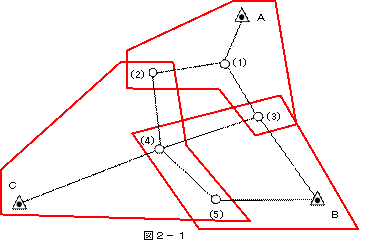| - PR - |
| - PR - |
|
< H19pm-No2-A:解答例 >
TSを用いた基準点測量とGPSを用いた基準点測量の相違点について述べる問題である。互いの測量方法について、その特徴をしっかりつかんでおく必要がある。以下に、解答例を記す。
|
|
< H19pm-No2-B:解答 >
基準点測量の作業工程に関する問題である。ア〜シ に入る適当な語句を考えると、次のようになる。
ア:踏査・選点 イ:計画立案 ウ:現況調査 エ:現地点検測量 オ:平均計画図 カ:点の記 キ:選点図 ク:埋設(埋標)ケ:観測図 コ:成果表 サ:精度管理表 シ:成果簿 |
|
< H19pm-No2-C:解答例 >
GPSを用いた基準点測量の観測図を作成する問題である。 「効率的な観測」とは少ないセッション数で平均図の基線を確保することである。重複基線は一本でよく、(1)(2)(3)(4)の四角形または(2)(3)(4)の三角形でセッション間の点検を行う(基線ベクトルの環閉合)。
|
|
< H19pm-No2-C:解答例 >
基準点測量の測量標や測量成果の利用に関する問題である。特に字数制限は無いが、(例)程度の字数は記入する必要がある。また、利用事例であるため、簡潔ながら具体的な記述が必要であると考える。
|