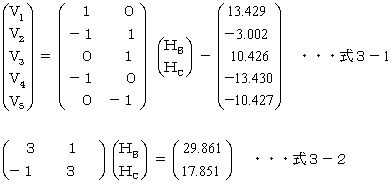| - PR - |
| - PR - |
|
<H19-3-A�F��>
�@�e�ݖ�ɂ��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B a.�ԈႢ�B �F�P |
|
<H19-3-B�F��>
�A�`�I�ɓK���Ȍ��Ă͂߁A����������������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�����덷�́A��ʂ� �ǒ�덷 �Ƃ��Ă�A�����I�Ȑ����̂��̂ł��顃`���`���O���x���� �������x�� �ł́A�\�����ɍ��܂ꂽ�����ь`�w���ŕW�ږڐ����͂��ތ덷������Ɋ܂܂��B���̌덷���ł�����菬�������邽�߂ɂ́A��C�̂�炬�₩���낤���傫�����́A �������� ��Z������B �������������ʂƂȂ��p����łȂ��ꍇ�ɐ�����덷�� �������덷 �Ƃ����B �W�ڂɕt���Ă���~�`�����킪�\���ɒ�������Ă��Ȃ��ꍇ�ɐ�����덷�́A �X�Βn �ŗݐς��鐫���������Ă���B
����āA�ł��K���Ȍ��̑g�����́A �ƂȂ�B
�F�S |
|
<H19-3-C�F��>
�W�ڕ�̌����́A�W�ڒ萔�FC0�C�c���W���F���C�C���FT0�CT�C���፷�F��H�Ƃ��Ď����ɂȂ�B ��C���oC0�{(T�|T0)���p��H
����ɖ�蕶�̐��l��������� ��C1���o0.005mm�{�i15�|20�j0.001mm�p�~23.7935��0.0mm�@ ��C2���o0.005mm�{�i20�|20�j0.001mm�p�~64.8412��0.3mm ����āA ��H1���|23.7935 ��H2���{64.8412�{0.0003���{64.8415�@ ��H����H1�{��H2���{41.0480
�d�ʂ��������Č덷��z��������W�����Z�o����� CH��AH�{��H1�{ ��h/3 CH��BH�|��H2�|2��h/3
�F�Q |
|
<H19-3-D�F��>
C�F�W���i1,0�̂����ꂩ�jdh�F��l�@L:�萔��
V���|C1 d h1�{C2 d h2 �| L
�A�F�A�̘H���͂a���b�ł��邩��A
�E�F�a�̌W�����a
�b�̌W�����a �b�̒萔�����a
�܂Ƃ߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�
�F�P |