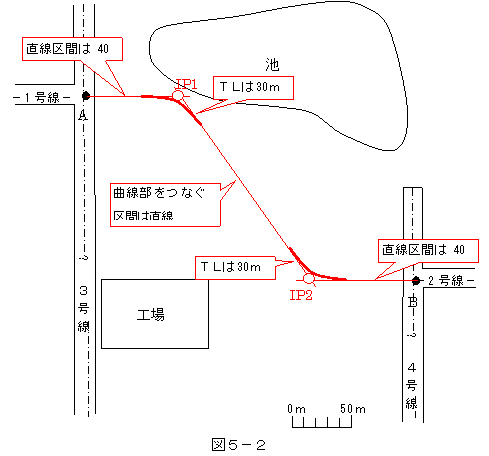| - PR - |
| - PR - |
|
��A
�� �A �� ���ʍ�Ɩ��F���S������ |
|
��B |
| ��C-1
���E�_�`�a�d�ň͂܂ꂽ�y�n�̖ʐς����߂�B
����āA90.00 ���Q |
| ��C-2 ���E�_�a���狫�E�_�b�̕����p
|
| ��C-3 ���E�_�a�C�p�̋��� �@��ӂ��A���E�_�d�a�p�̖ʐς��A10.00���Q �ƂȂ�悢�̂ŁA�܂��p�_���璼���d�a�ɑ��鍂���i���j�����߂�B �A �@�̐��l�ƁA�ڂd�a�p �� 53���ł��鎖�𗘗p���A�a�p�Ԃ̋����i���j�����߂�B |
| ��C-4 ���E�_�p�̍��W�����߂�B �w �� 12.00 �|�i1.11 �~ cos37���j�� 11.11 �� �x �� 30.00 �|�i1.11 �~ sin37���j�� 29.33 �� |
| ��D-1 �����Ԃ�������ׂ����� ���q��p������������ł́A���̑����Ԃ͎��̂悤�Ȏ����ɒ��ӂ��đI�肷��B ���͐�̗����Ɋւ��鎖���� �E���q�̗����������\���ɓ����鎖 �E�͐�f�ʂ��قڈ�l�ł��鎖 �E�͐S���قڒ����I�ȋ�Ԃł��鎖 ���͐�̎��ӊ��Ɋւ��鎖���� �E�Ί݂�e���ʂ����Ԃ̎��ʂ����ǂ��� �E���q�̓����f�ʂ���A��ʂ����̋������\���ł��鎖 ����L�̂悤�ȕ��͂�g���킹�āA50���ȓ��̕������Q�A�쐬����Ηǂ��B |
| ��D-2 ���q�̑I��⑪����@�Ɋւ��钍�ӎ����́A���̂悤�Ȏ����ɒ��ӂ��čs���悢�B �E���[�ɉ������A�h���i���������j�̕��q��p���� �E���q�̓����ʒu�́A�e�敪�f�ʂ̒����ɂȂ�悤�ɂ��� �E���q��������Ȃ��悤�A�u���h���ȂǂŃ}�[�N���� �E���q�����肵�đ�ꎋ�ʂ�����ʉ߂���悤�ɁA�����f�ʂƏ\���ȋ������m�ۂ��鎖 �E�ϑ��̑O��ɐ��ʂ̑�����s�� ����L�̂悤�ȕ��͂�g���킹�āA50���ȓ��̕������Q�A�쐬����Ηǂ��B |