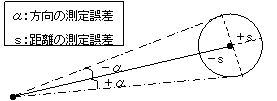| - PR - |
| - PR - |
|
<H18-4-A:解答>
平板測量において、許容誤差を仮定した場合の最大測定距離を求める問題である。次のような考え方で解答すると良い。
1.実測値における許容誤差を求める。 2.方向、距離の各測定誤差を相対誤差とし、複合誤差を求める。 3.複合誤差と許容誤差の比により、最大距離を求める。 解答: 3 |
|
<H18-4-B:解答>
変換公式の係数を求めるための方程式の穴埋め問題である。問題文と言うよりは、行列と連立一次方程式の関係が分かっていれば解ける問題である。 1.ア~カに入る数値を考えると、まず5の選択肢が除外される。 2.式4-2は、式4-1の変換式の係数を得るための方程式であるため、ア、ウ、オには、+の符号を持つ数値が入る。このため、3,4の選択肢は除外される。 3. 2.と同様に、第二式bの係数が符号を反することに注目し、この公式とは符号が逆になるものを探す。よって、2の数値の組合せが正しい。
解答: 2 |
|
<H18-4-C:解答>
アリダードを用いたスタジア法において、図上の水平位置誤差と分画読定値の読取誤差の許容範囲を仮定した場合に得られる、測定距離の最大測定値を求める問題である。次のような考え方で解答すればよい。
スタジア法による間接測定の公式は 問題文より、距離1mに対する誤差は 0.15m(1/500で0.3mm)、読定誤差を0.2分画である。 未知数がSとnの二つであるため、二式を立てその差を求めればよい。(未知数の一つが分母にあるので、実際は二次方程式になる。) 以下は二式の差⊿S = ±0.15mから考えたものである。
これに代入・通分して、 次に、定数項を移項すると、
上記のように厳密に解答するよりは、選択肢の中から10m、15m、20mをそれぞれスタジア公式にあてはめた方が早い。 10m:n=30.3分角、10.15m:n=29.5分角 差0.8分角 × 15m:n=20.0分角、15.15m:n=20.2分角 差0.2分角 ○ 20m:n=15.0分角、20.15m:n=14.9分角 差0.1分角 ×
解答: 3 |
|
<H18-4-D:解答>
数値地形モデル(DTM)に関する問題である。各選択肢について考えると、次のようになる。
1.○ 合成開口レーダでは煙で見えない部分でもDTM作成が可能 2.○ TS(トータルステーション)による測定で局所地域のDTM作成が可能 3.○ 既存地形図の等高線をディジタイズしても可能 4.× DTM作成を自動で行うと、森林地帯だと樹冠で計測してしまうおそれがある。 5.○ 数値表層モデルからフィルタリング処理によっても可能
解答: 4
合成開口レーダとは、マイクロ波を対象物に送信しそのエコー(反射したマイクロ波)を受信、分析して対象物の解析を行うものである。 一般的なレーダと異なる点は、軌道上を移動しながら、何度もマイクロ波の送受信を行う点であり、高解像度を得るために必要なレーダの径(開口面)を大きくせず、小型の径で得られるデータを合成して高解像度を得ようとするものである。このため、「合成開口」と言う名称で呼ばれる。 合成開口レーダは、航空機等に搭載され、雲や雨など天候、昼夜を問わず利用できるものであり、地表面の物性や起伏、凸凹、傾斜などを観測することができる。 <航空レーザ測量> 航空機に搭載した、レーザスキャナ(測距装置)を用いて、地表の位置(水平位置と高さ)を計測する測量方法である。また、レーザスキャナとは、進行方向に対して直角(横方向)にレーザ光を発射して地表から反射して戻ってくる時間差を調べて距離を決定するものである。 <数値表層モデル:DSM:Digital Surface Model> 航空レーザ測量で直接得られる高さのデータであり、建物や樹木などの高さを含んだものである。簡単に言えば、DSMのデータから地表面に達したデータを結び建物や樹木の高さを除いた(フィルタリング)ものをDEM(Digital Elevation Model)と呼ぶ。 ※DTMとDEMは同意義と考えてよい。 |