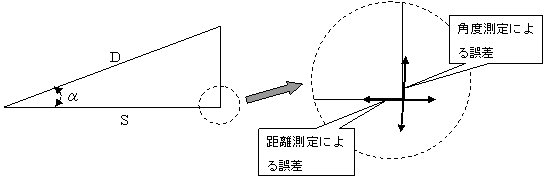| - PR - |
| - PR - |
|
<H18-2-A:解答>
測量作業における誤差について、明らかに間違っているものを選択する問題である。
1.正しい。 2.間違い。 3.正しい。 4.正しい。 5.正しい。
解答 2
|
|
<H18-2-B:解答>
光波測距儀による距離測定について問うている問題である。( ア )~( オ )には、次の語句が入る。
ア.短く:気温が高くなると測定距離は「短く」なる イ.短く:気圧が低くなると測定距離は「短く」なる ウ.気温:1℃の変化と1hPaの変化は3倍違うので変化が大きいのは「気温」 エ.長く:変調周波数が基準よりも高いと測定距離は「長く」なる オ.比例しない:位相差測定の誤差は位相差計の分解能(約1/1000)によるので「比例しない」
解答 2 |
|
<H18-2-C:解答>
測角と測距による精度の「つりあい」に関する問題である。標準偏差の累積であるため、誤差伝播の法則により、次のように考えればよい。
角度測定による誤差:D・sinα ×(4″/ρ″)= 0.015m 距離測定による誤差:cosα ×0.03m = 0.026m
誤差伝播の法則により、水平距離Sの標準偏差は、次のようになる。 M2 = m12 + m22 より、M =
解答 2 |
|
<H18-2-D:解答>
電子基準点について、明らかに間違っているものを選択する問題である。
1.正しい。 2.正しい。 5.正しい。
解答 3
|